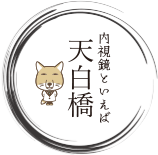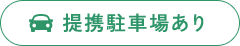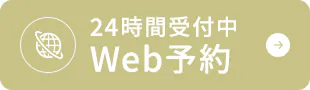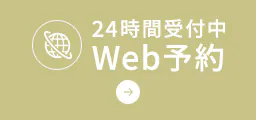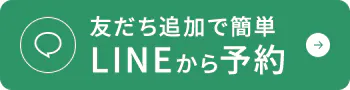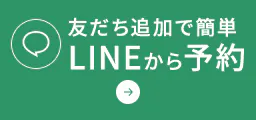さて、新生活が始まります。5月までに必ずでる不調を予想しましょう。
新生活、スタートしましたか?期待と不安が入り混じる春。実は、この時期、胃腸トラブルに見舞われやすいってご存知でしたか?環境の変化や生活リズムの乱れ、食生活の変化…知らないうちに胃腸は悲鳴を上げているかもしれません。内視鏡専門医として多くの患者さんを診てきた経験から、5月までに陥りやすい胃腸の不調を予測し、その原因と対策を詳しく解説します。新生活を気持ちよく乗り切るためのヒントが、きっと見つかるはずです。
お待たせし過ぎたかもしれませんし、誰もお待ちではないかもしれません。
内視鏡といえば天白橋!天白橋内科内視鏡クリニックの院長野田です。
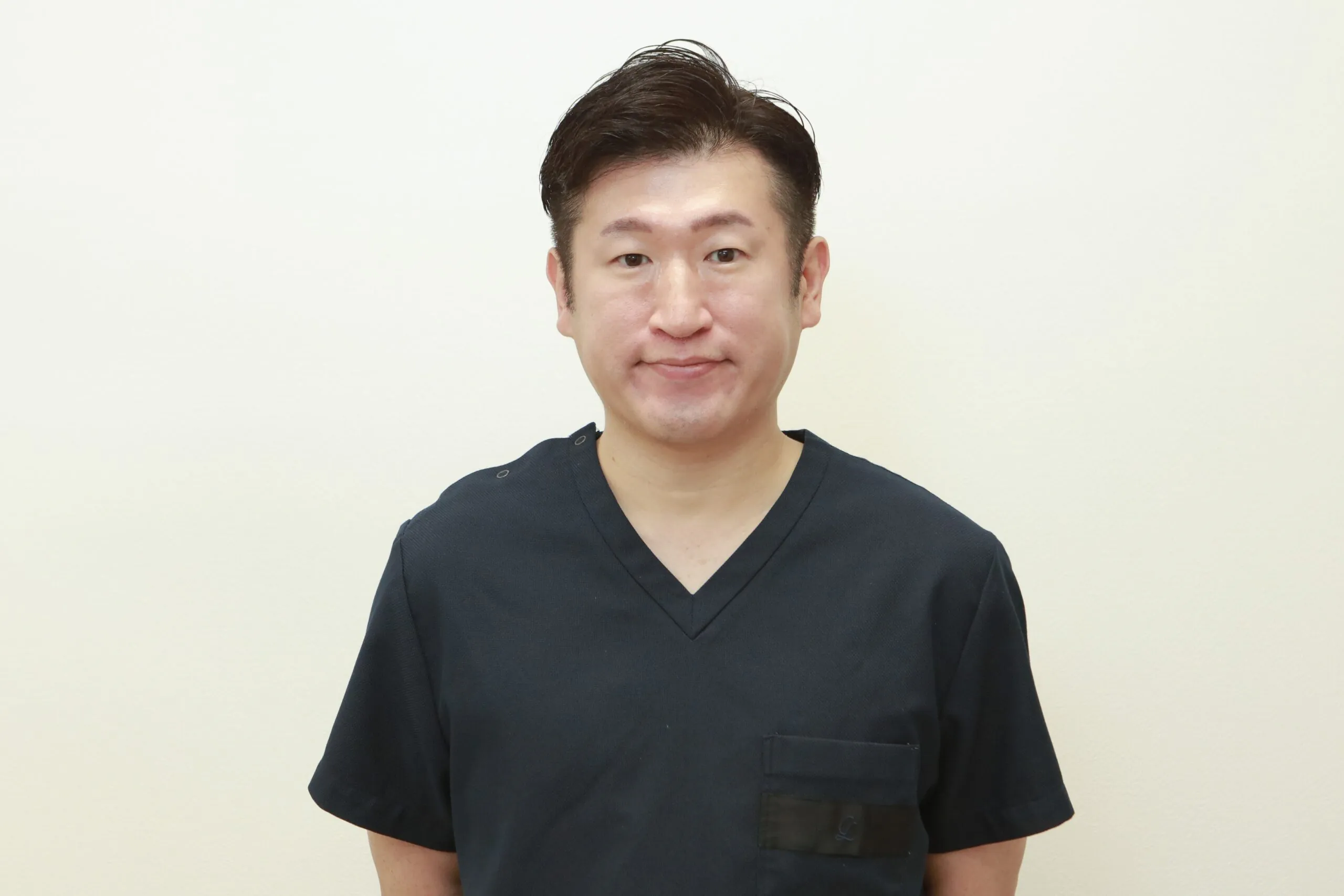
http://tenpakubashi-cl.com/staff/
尚、スタッフ募集中です。
https://tenpakubashi-cl.jbplt.jp/
新生活で胃腸の不調を感じやすい理由3選
新生活が始まり、期待とともに不安も抱えている方も多いのではないでしょうか。実は、新生活は環境の変化や生活リズムの乱れ、食生活の変化などが原因で、胃腸の不調を感じやすくなる時期です。
私自身も、新しい病院に赴任した当初は慣れない環境や人間関係に緊張し、食欲不振や胃もたれに悩まされた経験があります。内視鏡専門医として、多くの患者さんを診てきましたが、新生活に伴う胃腸の不調は決して珍しいことではありません。今回は、新生活で胃腸の不調を感じやすい3つの理由と、その具体的な内容について、医師の視点も交えながら詳しく解説します。天白橋内科内視鏡クリニックでは、内科全般の相談も受け付けていますので、どうぞお気軽にご相談ください。
環境の変化によるストレス
新生活は、新しい人間関係の構築や慣れない環境への適応など、何かとストレスがかかりやすい時期です。このストレスは、自律神経のバランスを崩し、胃腸の働きに大きな影響を与えます。自律神経は、交感神経と副交感神経の2つから成り、互いにバランスを取り合いながら身体の機能を調節しています。
通常の状態では、リラックスしている時に副交感神経が優位になり、胃腸の運動が活発化し、消化液の分泌が促進されます。反対に、緊張やストレスを感じている時には交感神経が優位になり、胃腸の運動は抑制され、消化液の分泌も低下します。
新生活に伴うストレスは、交感神経を過剰に優位にさせるため、胃の運動が滞り、消化不良や胃もたれ、便秘などを引き起こしやすくなります。反対に、ストレスに対する反応には個人差があり、中には副交感神経が過剰に反応し、胃酸の分泌が増加して胃痛や胸やけなどを引き起こす方もいます。
新生活におけるストレスによる胃腸の不調を予防・改善するためには、ストレスを軽減するための工夫が重要です。適度な運動、趣味の時間、リラックスできる音楽、アロマテラピーなど、自分に合ったストレス解消法を見つけることが大切です。また、睡眠不足もストレスを増大させるため、規則正しい睡眠習慣を心がけましょう。
生活リズムの乱れ
新生活が始まると、通勤・通学時間や仕事の開始・終了時刻などが変わり、生活リズムが乱れがちです。人間の体は一定のリズムで生活することを前提にできています。このリズムが崩れると、自律神経のバランスが乱れ、胃腸の働きにも悪影響を及ぼします。
特に、不規則な食事時間や睡眠不足は胃腸にとって大きな負担となります。朝食を抜いたり、夕食の時間が遅くなったりすると、胃が休まる時間がなくなり、消化不良や胃もたれといった症状が現れやすくなります。また、睡眠不足は胃腸の粘膜を修復する成長ホルモンの分泌を減少させ、胃炎や胃潰瘍のリスクを高める可能性も示唆されています。新生活でも、可能な限り規則正しい生活リズムを維持し、バランスの良い食事を3食きちんと摂り、十分な睡眠時間を確保することが重要です。
食生活の変化
新生活に伴い、一人暮らしを始めたり、職場や学校の近くに外食店が多かったりするなど、食生活が大きく変化することもあります。外食やコンビニ食中心の生活になると、栄養バランスが偏り、食物繊維の摂取量が不足しがちです。食物繊維は腸内環境を整え、便秘の予防や改善に効果があります。また、脂肪分の多い食事や刺激の強い香辛料の過剰摂取は、胃腸に負担をかけ、下痢や腹痛などを引き起こす可能性があります。
加えて、食生活の変化がきっかけで機能性ディスペプシアという病気を発症、あるいは悪化させるケースも考えられます。機能性ディスペプシアとは、内視鏡検査などでは異常が見られないにもかかわらず、みぞおちの痛みや灼熱感、食後の膨満感、すぐにお腹いっぱいになるなどの症状が慢性的に続く病気です。最近の研究では、この機能性ディスペプシアは、腸と脳のコミュニケーションの障害に関連していると考えられており、胃腸の運動障害、内臓の過敏性、胃腸内細菌叢の変化、粘膜や免疫機能の変化、中枢神経系の変化などが複雑に絡み合って症状が現れるとされています。
新生活に伴う環境の変化や生活習慣の乱れが、機能性ディスペプシアの症状を悪化させる可能性があるため注意が必要です。新生活における食生活の変化による胃腸の不調を予防するためには、バランスの取れた食事を心がけることが重要です。主食・主菜・副菜を揃え、野菜や果物を積極的に摂りましょう。食物繊維が豊富な玄米、全粒粉パン、根菜類、海藻類、きのこ類などを積極的に食事に取り入れると良いでしょう。また、発酵食品であるヨーグルトや納豆なども、腸内環境を整えるのに役立ちます。もし症状が続く場合は、自己判断せずに医療機関を受診し、適切な検査や治療を受けるようにしてください。
5月までに起こるよくある胃腸の不調4選
新生活が始まり、環境の変化や生活リズムの乱れから、胃腸の不調を感じていませんか?私自身も内視鏡専門医として赴任したばかりの頃、慣れない環境でのストレスから胃の不調を経験しました。
天白橋内科内視鏡クリニックでは、内視鏡検査はもちろんのこと、内科全般のご相談も承っております。今回は、5月までに起こりやすい4つの代表的な胃腸の不調について、医師の視点から解説します。どうぞ最後までお読みいただき、少しでも不安を解消していただければ幸いです。
胃痛・腹痛
胃痛や腹痛は、みぞおちあたりやお腹全体に感じる痛みで、キリキリとした痛みや、鈍い痛み、締め付けられるような痛みなど、症状は人それぞれです。
原因としてまず考えられるのは、ストレスによる胃酸過多です。精神的な緊張は自律神経のバランスを崩し、胃酸の分泌を過剰に促進することがあります。過剰な胃酸は胃粘膜を刺激し、痛みを引き起こします。
また、食生活の変化も原因の一つです。新生活に伴い、外食が増えたり、食事の時間が不規則になったりすると、栄養バランスが崩れ、胃腸に負担がかかりやすくなります。脂っこい食事や刺激の強い香辛料の過剰摂取も、胃の粘膜を刺激し、痛みを引き起こす可能性があります。
さらに、環境の変化への適応に伴う自律神経の乱れも胃痛・腹痛を引き起こすことがあります。自律神経は、胃腸の運動や消化液の分泌を調節する役割を担っています。新生活によるストレスや生活リズムの乱れは、自律神経のバランスを崩し、胃の運動を阻害したり、消化液の分泌を減少させたりすることで、痛みや不快感を引き起こします。
そして、内視鏡検査では異常が見つからないにも関わらず、胃の痛みや不快感、もたれなどを慢性的に繰り返す「機能性ディスペプシア」も考えられます。機能性ディスペプシアは、従来は原因不明の病気とされてきましたが、近年の研究では、腸と脳のコミュニケーション障害に関連していると考えられています。胃腸の運動障害や内臓の過敏性、胃腸内細菌叢の変化、粘膜や免疫機能の変化、中枢神経系の変化など、様々な要因が複雑に絡み合って症状が現れるとされており、新生活に伴う環境の変化や生活習慣の乱れが症状を悪化させる可能性も懸念されています。
吐き気・嘔吐
吐き気や嘔吐は、胃の内容物を吐き出してしまう症状です。食中毒やウイルス性胃腸炎といった感染症が原因で起こることが多く、発熱や下痢を伴う場合もあります。また、ストレスや乗り物酔い、特定の食べ物に対するアレルギー反応なども原因となることがあります。
吐き気や嘔吐が続くと、体内の水分や電解質が失われ、脱水症状に陥る危険性があります。脱水症状が進むと、めまいやふらつき、意識障害などを引き起こす可能性もあるため、注意が必要です。
食欲不振・消化不良
食欲不振は、食べ物を食べたいという気持ちがわかない、あるいは食べられない状態です。消化不良は、食べたものがうまく消化されないために、胃もたれや胸やけ、げっぷなどの症状が現れる状態です。
新生活によるストレスや環境の変化、不規則な食生活などが原因となることが考えられます。ストレスは自律神経のバランスを崩し、胃腸の働きを低下させます。また、不規則な食生活は、胃腸に負担をかけ、消化不良を引き起こしやすくなります。
機能性ディスペプシアも、食欲不振や消化不良の原因となることがあります。機能性ディスペプシアでは、食後の膨満感や早期満腹感といった症状が現れるため、食事を十分に摂ることができず、食欲不振につながることがあります。
便秘・下痢
便秘は、便の排泄が3日以上なく、便が硬くて出にくい状態です。下痢は、水分を多く含んだ軟便や水様便が頻繁に排泄される状態です。
食物繊維や水分摂取の不足、運動不足といった生活習慣の乱れは便秘の大きな原因となります。食物繊維は便のかさを増やし、腸の蠕動運動を促進する働きがあります。水分が不足すると便が硬くなり、排泄しにくくなります。また、運動不足も腸の蠕動運動を低下させ、便秘を悪化させます。
一方、下痢は、主にウイルスや細菌による感染症が原因で起こります。食中毒やウイルス性胃腸炎などが代表的な例です。また、ストレスや特定の食品に対するアレルギー反応、過敏性腸症候群なども下痢の原因となることがあります。
便秘が続くと、腸内に老廃物が蓄積され、腹痛や腹部膨満感、吐き気などを引き起こすことがあります。また、下痢が続くと、体内の水分や電解質が失われ、脱水症状や栄養不足に陥る可能性があります。
新生活におけるストレスや環境の変化は、自律神経のバランスを崩し、便秘や下痢といった症状を誘発または悪化させる可能性があります。
天白橋内科内視鏡クリニックでできる胃腸不調の改善策3選
新生活が始まり、環境の変化や生活リズムの乱れから、胃腸の不調を感じてはいませんか?慣れない環境でのストレスや食生活の変化は、胃腸に大きな負担をかけます。私自身も、新しい病院に赴任した当初は、慣れない環境や人間関係から来るストレスで、食欲不振や胃もたれに悩まされた経験があります。
天白橋内科内視鏡クリニックでは、内視鏡専門医である院長が、内科全般の相談も承っております。今回は、皆様のつらい症状を改善するために、当院でできる胃腸不調の改善策を3つのステップに分けてご紹介します。丁寧な診察と的確な検査、そして患者様一人ひとりに最適な治療法で、皆様の健康をサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
診察・検査について
まずは、患者様のお話を詳しく伺うことから始めます。問診では、現在の症状、症状が現れ始めた時期、症状が悪化するタイミング、食生活、生活習慣、過去の病歴などについて、詳細に確認させていただきます。
次に、腹部の触診を行い、痛みや圧痛、腫瘤の有無などを確認します。この時、患者様ご自身も気づいていない小さな変化を見つける手がかりとなることもあります。
そして、問診や触診の結果を踏まえ、必要に応じて以下の検査を行います。それぞれの検査で何がわかるのか、なぜその検査が必要なのかを、わかりやすくご説明いたしますのでご安心ください。
- 血液検査: 炎症反応、貧血の有無、肝機能、腎機能、栄養状態などを調べます。例えば、炎症反応が高い場合は、体内で炎症が起きていることを示唆しており、胃腸炎などの可能性が考えられます。
- 便検査: 便潜血の有無、腸内細菌の状態、炎症の有無などを調べます。便潜血が陽性の場合、消化管のどこかで出血している可能性があり、精密検査が必要になります。
- 尿検査: 腎臓や膀胱の機能、脱水症状の有無などを調べます。脱水症状は、下痢や嘔吐が続いた際に起こりやすく、電解質バランスの異常につながる可能性があります。
- 内視鏡検査: 食道、胃、十二指腸の状態を直接観察し、炎症、潰瘍、ポリープ、腫瘍などの有無を調べます。当院は内視鏡検査に特化したクリニックであり、経験豊富な内視鏡専門医である院長が検査を担当いたします。検査に伴う苦痛や不安を最小限に抑えるよう、常に患者様の気持ちに寄り添った対応を心がけておりますので、ご安心ください。内視鏡検査で異常がない場合でも、上腹部痛や灼熱感、食後満腹感、早期満腹感などの症状が続く場合は、機能性ディスペプシアの可能性があります。機能性ディスペプシアとは、内視鏡などの検査では異常が見られないにもかかわらず、慢性的な消化器症状が現れる病気で、近年の研究では腸と脳のコミュニケーション障害に関連していると考えられています。
- 画像検査(腹部超音波検査、CT検査など): 必要に応じて、腹部臓器の状態を詳しく調べるために行います。超音波検査は、肝臓、胆嚢、膵臓、腎臓などの臓器の形態や大きさ、腫瘍の有無などを調べることができます。CT検査は、より詳細な臓器の断面像を得ることができ、腫瘍の有無やその広がりなどを評価するのに役立ちます。
具体的な治療法
検査結果に基づき、患者様一人ひとりの症状や状態に合わせた最適な治療法を提案いたします。その際、患者様のご希望も伺いながら、治療方針を決定していきます。
- 生活指導: 食生活の改善、ストレス軽減、適度な運動、十分な睡眠など、具体的な方法をアドバイスいたします。例えば、食物繊維を多く含む食品を積極的に摂る、刺激物を控える、よく噛んで食べる、腹八分目を心がける、などが挙げられます。
- 薬物療法: 症状に合わせて、胃酸を抑える薬、消化管の運動を調整する薬、腸内環境を整える薬、漢方薬などを処方します。機能性ディスペプシアの場合、症状に合わせて、プロトンポンプ阻害剤(胃酸の分泌を抑える薬)、H2受容体拮抗薬(胃酸の分泌を抑える薬)、胃運動促進薬(胃の運動を活発にする薬)などを処方することがあります。ヘリコバクター・ピロリ感染が確認された場合は、除菌療法を行います。
- 食事療法: 症状に合わせた食事内容や食事の摂り方について指導します。例えば、消化の良い食品を選ぶ、脂肪分の多い食事を控える、刺激の強い香辛料を控える、よく噛んで食べる、腹八分目を心がける、規則正しい時間に食事を摂る、などが挙げられます。
アクセス方法・診療時間
天白橋内科内視鏡クリニックは、名古屋市営地下鉄鶴舞線「原駅」より徒歩2分、名古屋市天白区に位置しています。近隣には提携駐車場も完備しており、お車でも公共交通機関でも通いやすいクリニックです。
診療時間アクセスはこちら→こちら
まとめ
新生活は、環境の変化や生活リズムの乱れから、胃腸の不調を起こしやすい時期です。ストレス、生活リズムの乱れ、食生活の変化は、胃腸に大きな負担をかけます。
胃痛、吐き気、食欲不振、便秘など、様々な症状が現れる可能性があり、これらの症状が続く場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
天白橋内科内視鏡クリニックでは、問診、触診、血液検査、便検査、内視鏡検査などを通して、患者さん一人ひとりの状態に合わせた適切な治療を提供しています。
新生活での胃腸の不調でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。きっと、あなたに合った解決策が見つかるはずです。
全ては患者さんの「もっと早く治療しとけばよかった・・・」を無くしたいから。
詳しくは当院のホームページ(←こちらをクリック)からどうぞ。

令和7年3月22日 天白橋内科内視鏡クリニック 野田久嗣
・医学博士
・日本内科学会認定内科医
・日本消化器病学会消化器病専門医
・日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医
参考文献
- Ford AC, Mahadeva S, Carbone MF, Lacy BE and Talley NJ. "Functional dyspepsia." Lancet (London, England) 396, no. 10263 (2020): 1689-1702.
追加情報
[title]: Functional dyspepsia.,
【要約】
ディスペプシアは、胃十二指腸領域に関連する症状の複合体であり、上腹部痛や灼熱感、食後満腹感、早期満腹感などを含む。
ディスペプシア患者の約80%は、症状の原因となる器質的異常が認められず、機能性ディスペプシアと診断される。
一般集団の健康な人の最大16%に機能性ディスペプシアが見られる。
リスクファクターには、精神疾患の合併、急性胃腸炎、女性、喫煙、非ステロイド性抗炎症薬の使用、ヘリコバクター・ピロリ感染などがある。
病態生理は完全には解明されていないが、腸と脳のコミュニケーション障害に関連しており、運動障害、内臓過敏症、胃腸内細菌叢、粘膜・免疫機能、中枢神経系の処理の変化などが関与すると考えられる。
機能性ディスペプシアの診断には、内視鏡検査で異常がないことを確認する必要があるが、典型的な症状を持つすべての患者に対して内視鏡検査を行う必要性は低い。55歳以上、または体重減少や嘔吐などの懸念事項のある患者に限定すべきである。
病態生理の理解が不十分なため、機能性ディスペプシアの治療は困難であり、多くの患者で慢性経過をたどり、症状は変動する。
ヘリコバクター・ピロリ陽性の機能性ディスペプシア患者には、除菌療法を行うべきである。
効果が認められている他の治療法には、プロトンポンプ阻害剤、H2受容体拮抗薬、胃運動促進薬、中枢神経調節薬などがある。
心理療法の役割は不確実である。
病態生理の理解が深まるにつれ、今後10年間で、初めて真の病気を改善する治療法が登場する可能性がある。
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33049222,
[quote_source]: Ford AC, Mahadeva S, Carbone MF, Lacy BE and Talley NJ. "Functional dyspepsia." Lancet (London, England) 396, no. 10263 (2020): 1689-1702.