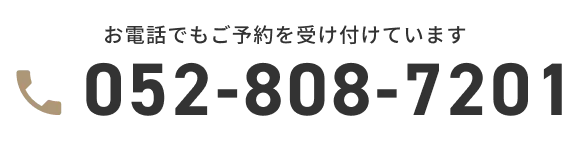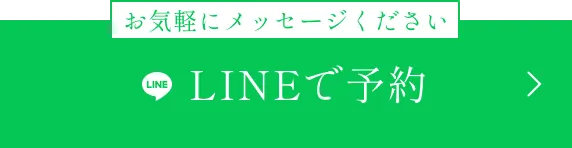慢性的な疲労感、倦怠感…まるで体に重りがついたよう、日常生活に支障をきたしていませんか? それはもしかしたら、慢性疲労症候群(ME/CFS)かもしれません。 原因不明の強い疲労感が6ヶ月以上続くこの病気は、休んでも回復せず、思考力や集中力の低下、頭痛、睡眠障害など様々な症状を伴います。 世界保健機関(WHO)も認めるこの疾患は、近年増加傾向にあり、特にコロナ禍後はその患者数が増加しているとの報告もあります。 「もう、何もできない…」と感じる前に、この難病の定義、診断基準、そして効果的な治療法について、専門家の解説を通して詳しく見ていきましょう。 あなたの症状と照らし合わせ、改善への一歩を踏み出しましょう。
【この記事の著者のご紹介】
みなさんお待たせしました。専門医がお答えシリーズです!
お待たせし過ぎたかもしれませんし、誰もお待ちではないかもしれません。
内視鏡といえば天白橋。内科もやっぱり天白橋。天白橋内科内視鏡クリニックの院長野田です。
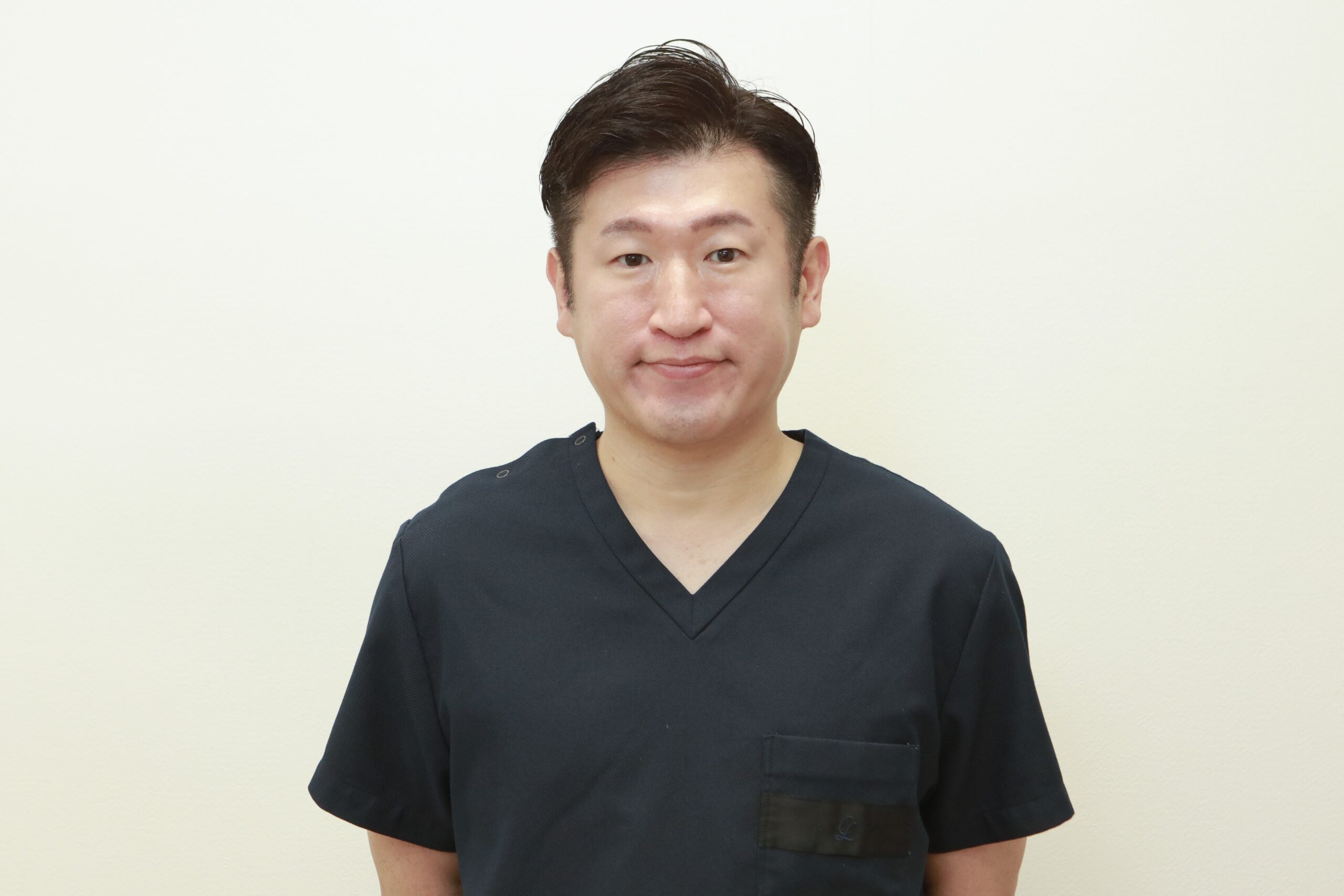
https://tenpakubashi-cl.com/staff/
https://tenpakubashi-cl.jbplt.jp/
目次
慢性疲労症候群の定義と診断基準
慢性的な疲労感や倦怠感は、多くの人が経験する症状です。もしかしたら慢性疲労症候群かもしれないと不安を抱えている方もいるかもしれません。この病気は診断が難しく、原因も完全には解明されていません。
当院は、内科、特に消化器内視鏡検査を専門とするクリニックですが、地域医療への貢献を目指し、風邪などの一般的な症状から、慢性疲労症候群のような診断が難しい疾患まで、幅広く対応しています。
このセクションでは、慢性疲労症候群の定義と診断基準について、内科医師の立場からわかりやすく解説します。ご自身の状況と照らし合わせながら読んでみてください。
慢性疲労症候群とは何か
慢性疲労症候群(Chronic Fatigue Syndrome: CFS)、または筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: ME/CFS)は、原因不明の強い疲労感や倦怠感が6ヶ月以上続き、日常生活に大きな支障をきたす病気です。
「慢性」という言葉には、6ヶ月以上症状が続いているという意味が含まれています。
普通の疲れと慢性疲労症候群の大きな違いは、休んでも回復しないことです。
例えば、普段なら週末にしっかり休めば解消する疲労感が、慢性疲労症候群の場合は、いくら休んでも取れない、あるいは少し動くとまたぶり返してしまう、といった状態が続きます。
身体的な疲労だけでなく、思考力や集中力の低下、頭痛、睡眠障害、微熱、リンパ節の腫れなど、さまざまな症状が現れることもあります。まるで身体のバッテリーが充電できなくなってしまったような状態です。
診断に必要な症状とは
慢性疲労症候群の診断は、国際的な診断基準に基づいて行われます。診断には、以下の条件を満たす必要があります。
-
主症状: 日常生活に支障をきたすほどの強い疲労感が6ヶ月以上持続し、他の病気が原因ではないこと。この疲労感は、安静にしても十分に回復しないことが重要です。例えば、以前は趣味のスポーツを楽しめていたのに、慢性的な疲労感のために、運動どころか日常生活にも支障が出ている、といった状況です。
-
必須症状: 以下の症状のうち、4つ以上が同時に6ヶ月以上持続していること。
- 思考力や集中力の低下:例えば、仕事でミスが増えたり、会議の内容が頭に入ってこなかったりする。
- 咽頭痛:風邪でもないのに喉が痛い、イガイガする。
- 頸部リンパ節や腋窩リンパ節の腫れ:首や脇の下にしこりのようなものに触れる。
- 筋肉痛:運動をした後のような痛みやだるさが続く。
- 関節痛:関節がズキズキ痛む。
- 頭痛:慢性的に頭痛がする。
- 睡眠障害:寝つきが悪い、夜中に何度も目が覚める、朝起きてもスッキリしない。
- 運動後、24時間以上続く全身倦怠感:軽い運動をした後でも、ひどい疲労感が翌日まで続く。
これらの症状は、他の病気でも見られることがあるため、慢性疲労症候群の診断は容易ではありません。
他の疾患との鑑別ポイント
慢性疲労症候群は、症状が多岐にわたるため、他の多くの病気と症状が似ており、鑑別が難しい病気です。例えば、甲状腺機能低下症、膠原病、うつ病、睡眠時無呼吸症候群、線維筋痛症などは、慢性疲労症候群と似たような疲労感や倦怠感を引き起こすことがあります。
感染症、特にCOVID-19の後遺症としても、慢性疲労症候群様の症状が現れるケースが報告されています。
鑑別診断を行うためには、血液検査、画像検査、睡眠検査など、さまざまな検査が必要となる場合があります。
慢性疲労症候群は、他の病気がないことを確認した上で診断されるため、問診や診察に加えて、詳しい検査が必要となることがあります。医療機関を受診し、専門医による適切な診断を受けることが重要です。
当院では、患者様一人ひとりの症状に真摯に向き合い、丁寧な問診と必要な検査を行い、慢性疲労症候群の診断、そして他の疾患の可能性についても慎重に検討します。お困りの際は、お気軽にご相談ください。
慢性疲労症候群の主な症状とその影響
慢性疲労症候群は、まるで体に重りがついたように、日常生活に大きな影を落とすことがあります。ただの疲労とは異なり、休んでも回復しないほどの強い疲労感が長期間続くことが特徴です。
以前は週末にリフレッシュしてまた一週間頑張ろうと思えていたのに、最近は休み明けも疲れが取れず、仕事にも集中できない…もしかしたら慢性疲労症候群かもしれません。
当院では、内視鏡検査をはじめとした消化器系の疾患を中心に診療していますが、地域医療への貢献という理念のもと、風邪などの一般的な症状から、慢性疲労症候群のような診断が難しい疾患まで、幅広く対応しています。
慢性疲労症候群は身体的な症状だけでなく、精神的な健康状態や日常生活にも大きな影響を及ぼします。このセクションでは、それぞれの影響について、内科医師の立場から具体的に解説します。
よく見られる身体的症状
慢性疲労症候群の身体的症状は人それぞれで、その現れ方は多様です。症状の重さや組み合わせも一人ひとり異なり、まるでモザイク模様のようです。
例えば、ある方は強い疲労感と微熱に悩まされ、別の患者さんは頭痛と筋肉痛に苦しむかもしれません。また、リンパ節の腫れや、喉の痛みを感じる方もいます。
これらの症状は、日によって変化することもあります。昨日まで比較的調子が良かったのに、今日は体が重くて何もできない、といったように、症状の波があることが特徴です。
| 症状 | 具体的な症状 |
|---|---|
| 強い疲労感 | 朝起きた時から体が重だるく、鉛のように感じられる。階段を上るだけで息切れがしたり、少し家事をするだけでぐったりしてしまう。 |
| 微熱 | 37度前後の微熱が続く。平熱が低い人にとっては、いつもより体温が高い状態が続くだけでも、倦怠感を強く感じる場合もある。 |
| 頭痛 | 頭全体が締め付けられるような痛み、ズキズキとした痛み、後頭部が重いなど、頭痛の種類もさまざま。慢性疲労症候群では、緊張型頭痛や片頭痛の頻度が増すことも少なくない。 |
| 筋肉痛 | 運動をした後のような筋肉痛が、安静時にも続く。特に、肩や首、背中などに痛みを感じやすい。 |
| 関節痛 | 関節がズキズキと痛む、あるいはこわばる感じがする。朝起きた時に関節が硬く感じることが多い。 |
| リンパ節の腫れ | 首や脇の下のリンパ節が腫れて、触ると痛みを感じる場合もある。風邪をひいた時のようなリンパ節の腫れと異なり、長引くことが特徴。 |
これらの症状は他の病気でも見られるため、これらの症状があるからといって必ずしも慢性疲労症候群であるとは限りません。重要なのは、これらの症状が6ヶ月以上続き、日常生活に支障をきたすほど強いということです。
精神的健康への影響
慢性疲労症候群は、心にも大きな負担をかけます。身体の不調が続くと、気分が落ち込みやすくなり、何事にも意欲がわかなくなってしまうことがあります。
例えば、以前は趣味のガーデニングを楽しんでいた方が、慢性的な疲労感のために庭に出る気力もなくなり、楽しみを失ってしまう、といったケースもあります。
また、集中力や記憶力の低下もよく見られる症状です。仕事のミスが増えたり、会議の内容が頭に入ってこなかったり、日常生活でも物忘れが増えたりすることがあります。
さらに、慢性的な痛みや不調、そして周囲の理解が得られないことなどから、不安感が強まり、精神的に追い詰められてしまう方も少なくありません。
日常生活への支障とその対処法
慢性疲労症候群は、日常生活のあらゆる場面に影響を及ぼします。仕事や家事はもちろん、趣味やレジャー、友人との付き合いなど、今まで当たり前にできていたことができなくなることがあります。
例えば、以前は活発に外出していた方が、慢性的な疲労感のために外出を控えがちになり、社会的な孤立感を深めてしまう、といったケースも少なくありません。
慢性疲労症候群の症状は、日によって、あるいは時間帯によって変動することがあります。「波」があるのです。そのため、自分の状態に合わせて活動量を調整することが大切です。
無理をせず、こまめに休息を取り入れる、自分のペースでできる範囲のことを行うなど、工夫してみましょう。
また、症状を悪化させる要因を特定し、できるだけ避けるようにすることも重要です。例えば、ストレスや過労、睡眠不足などが症状を悪化させる場合は、これらの要因を避けるように意識しましょう。
当院では、患者様一人ひとりの症状に寄り添い、丁寧な問診と検査に基づいて診断を行います。慢性疲労症候群は、診断が難しく、他の病気との鑑別も重要となるため、専門医の診察を受けることが大切です。
日常生活への支障を最小限に抑え、より良い生活を送るためにも、お一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
慢性疲労症候群の治療法と回復の見込み
慢性疲労症候群は、原因不明の強い疲労感が長期間続く厄介な病気です。まるで目に見えない重りに縛られているかのように、日常生活に大きな支障をきたします。
当院は、名古屋市天白区の天白橋内科内視鏡クリニックです。地下鉄原駅より徒歩2分、提携駐車場も完備しており、アクセス良好です。内視鏡検査をはじめとした消化器疾患の専門クリニックですが、地域医療への貢献という理念のもと、風邪症状から慢性疲労症候群のような診断が難しい疾患まで、幅広く診療を行っています。医療アートメイクやエクソソーム点滴療法にも対応しています。
慢性疲労症候群の治療は、完治を目指すというよりは、症状をコントロールし、日常生活の質を向上させることを目標とします。回復の見込みは人それぞれで、年齢や生活環境、症状の重さなどによって大きく異なります。焦らず、じっくりと治療に取り組むことが大切です。
このセクションでは、慢性疲労症候群の治療法と回復の見込みについて、内科医師の立場から具体的な解説を加えながら詳しく説明します。
一般的な治療法の種類
慢性疲労症候群の治療は、患者さん一人ひとりの症状や生活状況に合わせて、オーダーメイドで組み立てられます。大きく分けて、薬物療法、認知行動療法、運動療法の3つのアプローチがあります。
-
薬物療法: 慢性疲労症候群に伴う様々な症状を緩和するために、お薬を使う治療法です。例えば、強い疲労感や倦怠感には抗うつ薬、睡眠障害には睡眠導入剤、痛みには鎮痛剤などが処方されることがあります。これらの薬は、あくまで症状を和らげるための対症療法であり、慢性疲労症候群そのものを根本的に治すものではありません。
当院では、患者さんの症状や体質に合わせた適切な薬剤を選択し、副作用にも配慮しながら慎重に処方いたします。
-
認知行動療法: これは、考え方や行動パターンを変えることで、症状への対処能力を高める治療法です。「疲れたら休む」という考え方ではなく、「疲れていても少し体を動かしてみる」「短時間でも集中して作業に取り組んでみる」など、行動を少しずつ変えていくことで、症状の悪循環を断ち切り、日常生活の質を向上させることを目指します。
例えば、以前は趣味の読書を長時間楽しめていたのに、慢性疲労症候群を発症してからは、集中力が続かず、数分しか読書ができなくなってしまったとします。認知行動療法では、まずは1分間だけ読書をしてみる、次に2分間読書をしてみる、といったように、少しずつ読書時間を延ばしていく練習をすることで、読書への意欲を取り戻し、集中力を高めていくことを目指します。
-
運動療法: 無理のない範囲で軽い運動を続けることで、体力の回復や睡眠の質の改善を図ります。ウォーキングやストレッチ、ヨガ、太極拳など、軽い運動から始め、徐々に運動量を増やしていくことが大切です。いきなり激しい運動を行うと、かえって症状が悪化してしまう場合があるので、医師や理学療法士の指導のもと、自分のペースで進めていくことが重要です。
例えば、最近ではCOVID-19の後遺症として慢性疲労症候群様の症状が現れるケースが報告されており、その治療においても運動療法が有効とされています。
これらの治療法は、単独で行うよりも、組み合わせて行うことでより効果的になります。
副作用やリスクについての考慮
薬物療法では、薬の種類によっては副作用が現れる可能性があります。例えば、抗うつ薬では眠気や吐き気、口の渇き、便秘など、睡眠薬では依存性やふらつきなどの副作用が挙げられます。副作用が強い場合は、我慢せずに医師に相談し、薬の種類や量を調整してもらうことが大切です。
認知行動療法や運動療法は、適切に行えば副作用のリスクは低いですが、無理をすると症状が悪化してしまう可能性があります。自分のペースで進めること、そして医師や理学療法士の指示に従うことが重要です。
生活習慣の改善と予防策
慢性疲労症候群の症状を改善し、再発を予防するためには、日常生活における工夫も欠かせません。規則正しい生活、バランスの取れた食事、適度な運動、ストレス管理、そしてアルコールやカフェインの摂取制限などは、慢性疲労症候群の症状だけでなく、健康全般に良い影響を与えます。
- 規則正しい生活: 睡眠時間をしっかりと確保し、毎日同じ時間に寝起きする習慣をつけましょう。睡眠不足は疲労感を増幅させるため、質の高い睡眠を心がけることが重要です。
- バランスの取れた食事: 栄養バランスの良い食事を心がけ、免疫力を高めましょう。特に、ビタミンやミネラルが不足すると疲労感が増すことがあるため、積極的に摂取するようにしましょう。
- 適度な運動: 軽い運動を習慣的に行い、体力を維持しましょう。ウォーキングやストレッチなど、無理のない範囲で体を動かすことが大切です。
- ストレス管理: ストレスを溜め込まないように、趣味やリラックスできる活動を取り入れましょう。ストレスは慢性疲労症候群の症状を悪化させる大きな要因となるため、自分なりのストレス解消法を見つけることが重要です。
- アルコールやカフェインの摂取制限: 過度な摂取は睡眠の質を低下させ、症状を悪化させる可能性があります。
これらの生活習慣を改善することで、慢性疲労症候群の症状をコントロールし、より快適な生活を送ることができるでしょう。当クリニックでは、患者様一人ひとりの状態に合わせた治療法をご提案いたします。お一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
まとめ
慢性疲労症候群は、原因不明の強い疲労感が6ヶ月以上続く病気で、日常生活に大きな支障をきたします。 診断は難しく、他の病気との鑑別も必要です。治療は完治を目指すのではなく、症状のコントロールと生活の質の向上を目指します。薬物療法、認知行動療法、運動療法など、患者さんの状態に合わせた治療法が用いられます。 大切なのは、無理せず自分のペースで治療を進めることです。規則正しい生活、バランスの良い食事、適度な運動、ストレス管理なども重要です。 症状に悩まれている方は、一人で抱え込まず、早めに医療機関を受診し、専門医に相談しましょう。 私たち医療チームは、あなたをサポートします。
全ては患者さんの「もっと早く治療しとけばよかった・・・」を無くしたいから。
詳しくは当院のホームページ(←こちらをクリック)からどうぞ。



令和7年4月11日
天白橋内科内視鏡クリニック 野田久嗣
・医学博士
・日本内科学会認定内科医
・日本消化器病学会消化器病専門医
・日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医
参考文献
- Grach SL, Seltzer J, Chon TY, Ganesh R. Diagnosis and Management of Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome. Mayo Clinic proceedings 98, no. 10 (2023): 1544-1551.
追加情報
ミオルガニック脳脊髄炎/慢性疲労症候群の診断と管理
【要約】
- ポイント1: ミオルガニック脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)は、しばしば感染に先行する慢性神経疾患である。
- ポイント2: 最近の研究では、ミオルガニック脳脊髄炎/慢性疲労症候群とCOVID後症候群(長期COVIDまたはCOVID後遺症)の重複があり、複数の研究ではCOVID後症候群の患者の半数がミオルガニック脳脊髄炎/慢性疲労症候群の基準を満たしていると推定されている。
- ポイント3: 当レビューでは、ミオルガニック脳脊髄炎/慢性疲労症候群の一般的なアプローチについて、診断、評価、および管理戦略について簡潔に説明している。
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37793728
,
[quote_source]: Grach SL, Seltzer J, Chon TY and Ganesh R. “Diagnosis and Management of Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome.” Mayo Clinic proceedings 98, no. 10 (2023): 1544-1551.