現代社会において、アレルギー疾患は増加の一途を辿っています。花粉症や食物アレルギーだけでなく、実は消化器症状もアレルギーが原因であるケースが増えていることをご存知でしょうか?くしゃみ、鼻水、かゆみといった分かりやすい症状から、腹痛や下痢といった消化器症状まで、アレルギーは私たちの体に様々な影響を及ぼします。
この記事では、アレルギー反応のメカニズムから、代表的なアレルギー疾患の種類、最新の研究知見まで、分かりやすく解説します。アレルギーの症状でお悩みの方、もしかしたらアレルギーかも?と不安に思っている方、ぜひご一読ください。もしかすると、あなたの抱える不調の鍵が、この記事で見つかるかもしれません。
メルスモンサプリをECサイトで絶賛発売中!
秘密のパスワードは【tenkitsune 】テンキツネです。
『狐の薬箱』→こちら
【この記事の著者のご紹介】
みなさんお待たせしました。専門医がお答えシリーズです!
お待たせし過ぎたかもしれませんし、誰もお待ちではないかもしれません。
内視鏡といえば天白橋。内科もやっぱり天白橋。天白橋内科内視鏡クリニックの院長野田です。
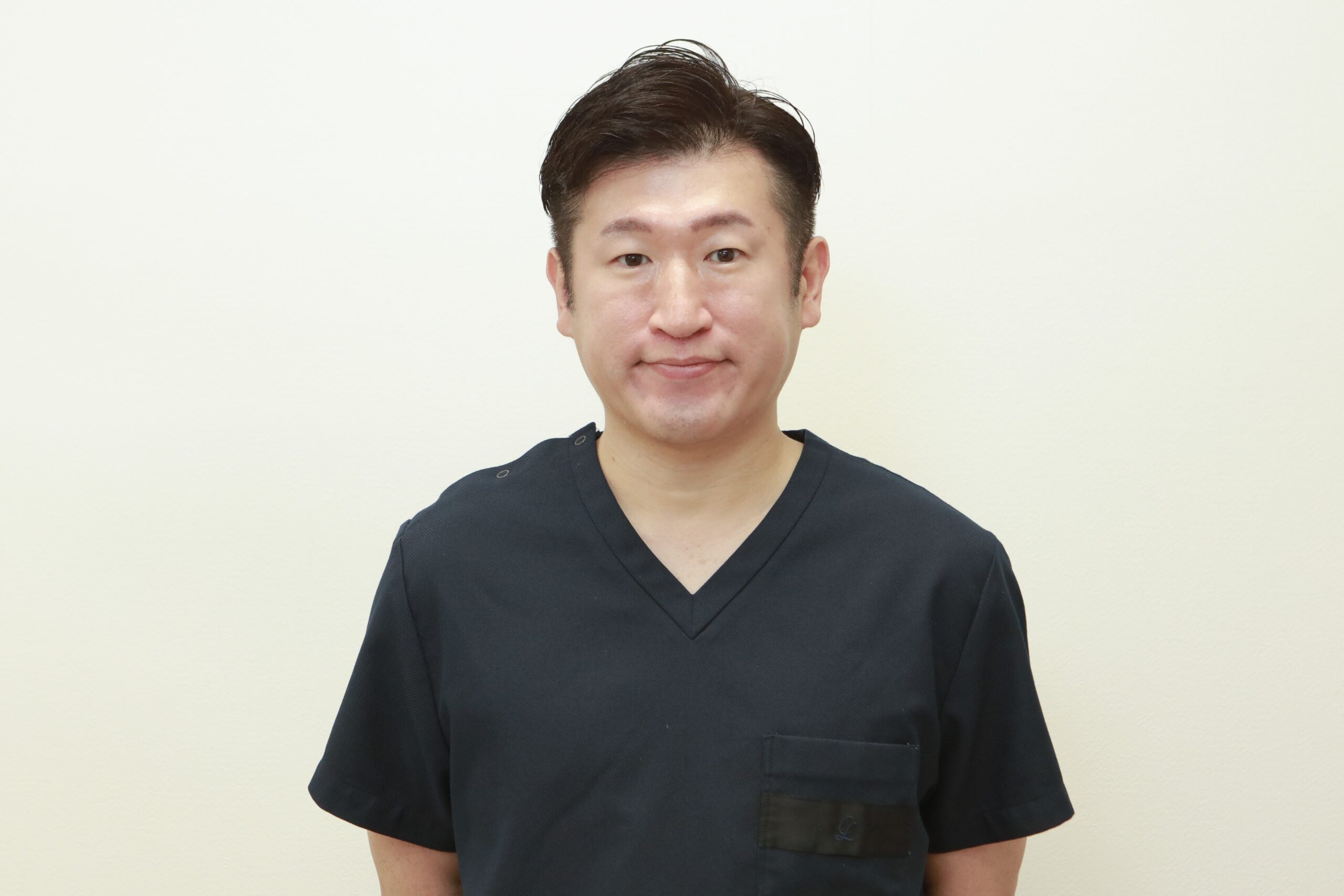
https://tenpakubashi-cl.com/staff/
https://tenpakubashi-cl.jbplt.jp/
アレルギー疾患とは?原因・症状・種類を解説
「アレルギー」と聞くと、花粉症や食物アレルギーを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。実際、アレルギー疾患は現代社会で増加傾向にあり、多くの方が何らかのアレルギー症状に悩まされています。私自身も、クリニックで診察する患者さんの訴えの中に、アレルギー関連の症状が占める割合は年々増加していると感じています。
アレルギーとは、本来無害な物質(花粉、ダニ、ハウスダスト、食物など)に対して、体が過剰に反応してしまうことで起こる疾患です。この「過剰反応」は、免疫システムの誤作動によって引き起こされます。免疫システムは、ウイルスや細菌といった有害な異物から体を守るための防御システムですが、アレルギー体質の人は、無害な物質にも攻撃を仕掛けてしまうのです。その結果、くしゃみ、鼻水、かゆみ、湿疹など、様々な不快な症状が現れます。
アレルギー反応のメカニズム
アレルギー反応は、複雑な免疫学的メカニズムによって引き起こされます。簡単に説明すると、以下の流れでアレルギー症状が現れます。
- 感作: 初めてアレルゲン(アレルギー反応を引き起こす物質)が体内に入ると、体はそれを異物として認識し、IgE抗体という特殊な抗体を産生します。このIgE抗体は、肥満細胞と呼ばれる免疫細胞の表面に結合します。
- 再曝露: 再び同じアレルゲンが体内に入ると、肥満細胞表面に結合していたIgE抗体と結合します。
- 化学伝達物質の放出: IgE抗体とアレルゲンが結合すると、肥満細胞からヒスタミンなどの化学伝達物質が放出されます。
- アレルギー症状の発現: ヒスタミンは、血管拡張、平滑筋収縮、粘液分泌などの作用を引き起こし、くしゃみ、鼻水、かゆみ、湿疹といったアレルギー症状を引き起こします。
アレルギー疾患の代表的な種類
アレルギー疾患は、原因となるアレルゲンや症状が現れる部位によって、様々な種類に分けられます。主なアレルギー疾患を以下に示します。
- アレルギー性鼻炎: 花粉、ダニ、ハウスダストなどが原因で、鼻水、鼻づまり、くしゃみなどの症状が現れます。季節性と通年性があります。
- 気管支喘息: アレルゲンや刺激物によって気管支が狭くなり、咳、痰、呼吸困難などの症状が現れます。アレルギー性のもの以外にも、運動誘発性喘息、感染性喘息などがあります。
- アトピー性皮膚炎: ダニ、ハウスダスト、食物などが原因で、皮膚に強いかゆみと湿疹が現れます。乳児期、小児期、成人期と年齢によって症状や好発部位が変化します。
- 食物アレルギー: 特定の食品を摂取することで、じんましん、嘔吐、下痢、呼吸困難などの症状が現れます。原因食物は鶏卵、牛乳、小麦が特に多く、乳幼児期に発症しやすいです。
- 薬物アレルギー: 薬剤に対してアレルギー反応を起こし、発疹、かゆみ、呼吸困難、アナフィラキシーショックなどの症状が現れます。様々な薬剤が原因となりえます。
アレルギーの症状(くしゃみ、鼻水、かゆみ、湿疹など)
アレルギーの症状は多様で、その程度も軽度から重度まで様々です。以下に代表的な症状をまとめました。
- 呼吸器症状: くしゃみ、鼻水、鼻づまり、咳、痰、呼吸困難、喘鳴(ゼーゼー、ヒューヒューという音)
- 皮膚症状: かゆみ、湿疹、じんましん、皮膚の赤み、腫れ
- 消化器症状: 腹痛、下痢、嘔吐、便秘
- その他: 目のかゆみ、涙目、充血、頭痛、倦怠感
アレルギーになりやすい人の特徴
アレルギーは、遺伝的要因と環境的要因の両方が関与して発症すると考えられています。アレルギーになりやすい人の特徴として、以下のようなものがあります。
- 家族歴: 家族にアレルギー疾患を持つ人がいる場合、アレルギーを発症するリスクが高くなります。
- アトピー素因: アトピー性皮膚炎、気管支喘息、アレルギー性鼻炎のいずれか、または複数を発症しやすい体質のことです。
- 生活習慣: ストレス、睡眠不足、食生活の乱れ、喫煙などもアレルギー発症のリスクを高める可能性があります。
- 環境要因: 大気汚染、ダニ、ハウスダスト、ペットの毛などもアレルギー症状を悪化させる要因となります。
精神的な健康状態もアレルギー疾患と関連があることが最近の研究で示唆されています。アレルギー症状が強いと日常生活に支障をきたし、精神的な負担も大きくなります。また、不安や抑うつなどの精神的なストレスは、アレルギー症状を悪化させる可能性があります。
アレルギー疾患と合併しやすい病気
アレルギー疾患は、他の病気と合併しやすいことが知られています。例えば、アレルギー性鼻炎の人は、副鼻腔炎や中耳炎を合併しやすくなります。アトピー性皮膚炎の人は、気管支喘息やアレルギー性結膜炎を合併することがあります。
アレルギー疾患を合併すると、症状のコントロールが難しくなる場合もあります。当院では、患者さん一人ひとりの症状や合併症の有無を丁寧に評価し、適切な治療方針を決定しています。些細な症状でもお気軽にご相談ください。
消化器内科で診るアレルギー疾患
アレルギー疾患は多岐に渡り、その症状は皮膚や呼吸器だけでなく、消化器にも現れることがあります。実際、私は内科・内視鏡クリニックの院長として、日々多くの患者さんを診察する中で、消化器症状を訴える方の原因がアレルギーであるケースに数多く遭遇しています。今回は、消化器内科で扱うアレルギー疾患について、具体的な症例や最新の研究知見を交えながら解説します。当院は内科・内視鏡専門医が、風邪などの一般的な症状から内視鏡検査、アレルギー疾患、更には医療アートメイクやエクソソーム点滴療法まで、内科全般の相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
食物アレルギー(卵、牛乳、小麦など)
食物アレルギーは、特定の食品を摂取した際に、じんましん、かゆみ、呼吸困難といったアレルギー症状が現れる疾患です。原因となる食品は卵、牛乳、小麦をはじめ様々ですが、特にこれら3つは「三大アレルゲン」と呼ばれ、食物アレルギーの原因食物として頻度が高い食品です。
食物アレルギーの怖いところは、ごく少量の摂取でも重篤なアナフィラキシーショックを引き起こす可能性があることです。アナフィラキシーショックは、血圧の急激な低下、呼吸困難、意識障害などを引き起こす生命に関わる危険な状態で、迅速な対応が求められます。
例えば、先日当院を受診された20代の女性は、友人とケーキを食べた30分後に、全身のじんましん、呼吸困難、意識レベルの低下といったアナフィラキシーショックの症状を呈し、救急搬送されてきました。問診の結果、彼女は小麦アレルギーの既往があり、そのケーキに小麦粉が含まれていたことが判明しました。幸い迅速な処置により回復しましたが、これは食物アレルギーの危険性を示す一例です。食物アレルギーは、アレルギー疾患の中でも特にアナフィラキシーを起こしやすい疾患です。
食物アレルギーの診断には、問診、血液検査、皮膚テストなどを行います。原因食品を特定するために、除去食試験や負荷試験を行うこともあります。除去食試験とは、疑わしい食品を一定期間除去し、症状が改善するかを確認する検査です。負荷試験は、少量の疑わしい食品を摂取し、アレルギー反応の有無を確認する検査です。負荷試験は医師の管理下で行われる必要があり、アナフィラキシーショックのリスクもあるため、慎重に実施する必要があります。治療の基本は、原因となる食品を除去することですが、日常生活で完全に除去することは非常に困難です。そのため、医師の指導のもと、摂取量を調整しながら生活していくことが重要です。
薬物アレルギー
薬物アレルギーは、特定の薬剤に対してアレルギー反応を起こす疾患です。薬物アレルギーは服用後すぐに症状が現れる場合もあれば、数日後に現れる場合もあります。症状は発疹、かゆみ、発熱など多様で、重篤な場合はアナフィラキシーショックを起こすこともあります。
薬物アレルギーの診断には、問診、血液検査、皮膚テストなどを行います。疑わしい薬剤を特定するために、薬剤負荷試験を行うこともあります。薬剤負荷試験は、少量の薬剤を服用し、アレルギー反応の有無を確認する検査ですが、アナフィラキシーショックのリスクもあるため、慎重に実施する必要があります。治療の基本は、原因薬剤の服用を中止することです。やむを得ず使用する必要がある場合は、医師と相談の上、代替薬の使用や減感作療法を検討します。減感作療法は、少量の薬剤を繰り返し投与することで体を薬剤に慣れさせる治療法です。
アレルギー性腸炎
アレルギー性腸炎は、特定の食品に対するアレルギー反応が原因で、下痢や腹痛といった消化器症状が現れる疾患です。特に乳幼児に多くみられ、原因食品は牛乳、卵、小麦などです。症状は慢性的な下痢、血便、腹痛、嘔吐などがあり、体重増加不良や貧血を伴うこともあります。
アレルギー性腸炎の診断には、問診、血液検査、便検査などを行います。原因食品を特定するために、除去食試験や負荷試験を行う場合もあります。治療の基本は原因食品の除去ですが、乳幼児期は成長・発達に重要な時期なので、栄養状態に十分配慮する必要があります。医師の指導のもと、適切な栄養管理を行いながら除去食を継続することが重要です。
好酸球性消化管疾患(EGID、好酸球性食道炎など)
好酸球性消化管疾患(EGID)は、消化管に好酸球という白血球が異常に多く集まり、炎症を起こす疾患です。好酸球性食道炎はその代表的な疾患であり、食道に好酸球が浸潤し、炎症を起こします。de Bortoliら(2024)の報告によると、好酸球性食道炎は、最も頻度の高い好酸球性胃腸疾患であり、慢性的な2型免疫応答を介した食道の炎症性疾患です。症状は、嚥下困難(食べ物が飲み込みにくい)、胸やけ、腹痛などです。
好酸球性消化管疾患の診断には、内視鏡検査と生検が必要です。内視鏡検査で消化管粘膜を観察し、生検によって組織を採取して好酸球の数を調べます。Dellonら(2018)の報告によると、好酸球性食道炎の診断には、食道生検において高倍率視野あたり少なくとも15個の好酸球(または約60個/mm²)が必要です。治療には、ステロイド薬や食事療法などが用いられます。
過敏性腸症候群(IBS)との鑑別
過敏性腸症候群(IBS)は、腹痛、下痢、便秘といった症状が慢性的に繰り返される疾患ですが、炎症や潰瘍のような器質的な異常は見られません。アレルギー性腸炎や好酸球性消化管疾患と症状が似ているため、鑑別が重要になります。IBSは器質的異常がないため、内視鏡検査や血液検査などでは異常所見は認められません。
IBSの診断は、ローマ基準という診断基準を用いて行います。ローマ基準とは、機能性消化管疾患の診断基準であり、症状に基づいて診断を行います。治療は生活習慣の改善、薬物療法、精神療法など多岐に渡ります。ストレスや食生活なども症状に影響するため、患者さん一人ひとりに合わせた治療法を選択する必要があります。アレルギー性腸炎や好酸球性消化管疾患との鑑別には、詳細な問診や検査が必要となるため、医療機関への受診をお勧めします。
天白橋内科内視鏡クリニックでのアレルギー検査・治療
アレルギー症状は、くしゃみ、鼻水、目のかゆみといった比較的軽いものから、呼吸困難や意識障害といった生命に関わる重篤なものまで、実に様々です。症状の現れ方も人それぞれで、ご自身ではアレルギーと気づいていないケースも多く見られます。
当クリニックでは、内科全般、消化器内科、そしてアレルギー科にも対応しており、どの科を受診すべきか迷っている方も安心してご相談いただけます。
検査の流れと費用
当クリニックでは、患者さん一人ひとりの症状や生活背景を丁寧に伺うことから始めます。問診では、症状の種類、発症時期、症状の出現頻度や持続時間、過去の病歴、生活習慣、家族歴など、多岐にわたる情報をお伺いします。
問診に基づき、視診・触診などの診察、そして血液検査を行います。血液検査では、アレルギーの原因物質(アレルゲン)に対する特異的IgE抗体の量を測定します。このIgE抗体は、アレルギー反応において中心的な役割を果たす物質です。
皮膚テストでは、少量のアレルゲンを皮膚に塗布、あるいは注射し、アレルギー反応の有無を確認します。例えば、アレルギー性鼻炎の患者さんに花粉エキスを皮膚に少量つけて反応をみます。
これらの検査を通して、アレルギーの原因を特定していきます。費用は検査の種類や組み合わせによって異なりますが、3割負担の方で3,000円~5,000円程度が目安です。具体的な検査内容については、ご相談の上決定しますのでご安心ください。
治療方法(薬物療法、食事療法、生活指導など)
アレルギーの治療は、症状や原因、重症度によって様々です。当クリニックでは、患者さんの状態に合わせた最適な治療法を提案します。
薬物療法では、抗ヒスタミン薬、抗アレルギー薬、ステロイド薬などを用いて症状を緩和します。抗ヒスタミン薬はアレルギー反応で放出されるヒスタミンの働きを抑え、くしゃみ、鼻水、かゆみなどを軽減します。
食物アレルギーが原因の場合は、原因となる食品を特定し、除去食などの食事療法を行います。原因食品を特定するためには、除去食試験や負荷試験を行うこともあります。除去食試験とは、疑わしい食品を一定期間除去し、症状が改善するかを確認する検査です。負荷試験とは、少量の疑わしい食品を摂取し、アレルギー反応の有無を確認する検査です。負荷試験は医師の管理下で行われる必要があり、アナフィラキシーショックのリスクもあるため、慎重に実施する必要があります。
生活指導では、アレルゲンを避けるための環境整備や生活習慣の改善についてアドバイスします。例えば、ダニやハウスダストが原因となることが多いので、こまめな掃除を心がけることが重要です。
免疫療法(減感作療法)は、アレルギーの原因物質を少量ずつ投与することで体をアレルゲンに慣れさせ、アレルギー反応を起こりにくくする治療法です。アレルギー性鼻炎や気管支喘息などの治療に用いられます。
当院のアレルギー検査・治療の特徴
天白橋内科内視鏡クリニックは、内科全般に加え、消化器内科、アレルギー科にも対応しています。消化器系の症状を伴うアレルギー疾患にも幅広く対応可能です。
院長は内視鏡専門医であると同時に、内科全般にわたる豊富な経験を有しています。患者さん一人ひとりに寄り添い、丁寧な診療を心がけています。
アレルギーの症状は多彩で、他の疾患と非常によく似た症状を呈することもあります。例えば、慢性膵炎は腹痛を主訴とする疾患ですが、その腹痛はアレルギー疾患による腹痛と酷似している場合があります。当院では、このような鑑別が難しい症例にも対応可能です。
アクセス方法と診療時間
天白橋内科内視鏡クリニック
よくある質問
Q. アレルギー検査は予約が必要ですか?
A. 血液検査は予約制です。
Q. どのくらい時間がかかりますか?
A. 検査の種類や混雑状況にもよりますが、血液検査は約30分、皮膚テストは約1時間程度かかります。多少前後する場合があります。
Q. 結果説明はいつ聞けますか?
A. 血液検査の結果は1週間後、皮膚テストの結果は当日ご説明いたします。
Q. どんなアレルギー検査ができますか?
A. 血液検査では、食物アレルギー、花粉症、ダニアレルギーなど、様々なアレルギーの検査が可能です。皮膚テストでは、即時型アレルギー反応の有無を確認できます。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
まとめ
この記事では、アレルギー疾患の概要、種類、症状、検査方法、治療法などについて詳しく解説しました。アレルギーは身近な病気ですが、症状は多岐にわたり、重篤な症状を引き起こす可能性もあるため、正しい知識を持つことが大切です。
「もしかしてアレルギーかも?」と感じたら、自己判断せずに早めに医療機関を受診しましょう。天白橋内科内視鏡クリニックでは、アレルギーに関する様々なご相談に対応しています。内科全般、消化器内科はもちろんのこと、アレルギー科にも対応しているので、どの科を受診すべきか迷っている方もご安心ください。経験豊富な医師が、丁寧な問診と適切な検査で、あなたの症状の原因を究明し、最適な治療法をご提案します。些細なことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。
全ては患者さんの「もっと早く治療しとけばよかった・・・」を無くしたいから。
詳しくは当院のホームページ(←こちらをクリック)からどうぞ。



令和7年4月18日
天白橋内科内視鏡クリニック 野田久嗣
・医学博士
・日本内科学会認定内科医
・日本消化器病学会消化器病専門医
・日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医
参考文献
- Gardner TB, Adler DG, Forsmark CE, Sauer BG, Taylor JR, Whitcomb DC. ACG Clinical Guideline: Chronic Pancreatitis. The American journal of gastroenterology 115, no. 3 (2020): 322-339.
- Löhr JM, Beuers U, Vujasinovic M, et al. European Guideline on IgG4-related digestive disease – UEG and SGF evidence-based recommendations. United European gastroenterology journal 8, no. 6 (2020): 637-666.
- Dellon ES, Liacouras CA, Molina-Infante J, et al. Updated International Consensus Diagnostic Criteria for Eosinophilic Esophagitis: Proceedings of the AGREE Conference. Gastroenterology 155, no. 4 (2018): 1022-1033.e10.
- de Bortoli N, Visaggi P, Penagini R, et al. The 1st EoETALY Consensus on the Diagnosis and Management of Eosinophilic Esophagitis – Definition, Clinical Presentation and Diagnosis. Digestive and liver disease : official journal of the Italian Society of Gastroenterology and the Italian Association for the Study of the Liver 56, no. 6 (2024): 951-963.
- Conway AE, Verdi M, Kartha N, et al. Allergic Diseases and Mental Health. The journal of allergy and clinical immunology. In practice 12, no. 9 (2024): 2298-2309.
追加情報
[title]: ACG Clinical Guideline: Chronic Pancreatitis.
慢性膵炎に関するACG臨床ガイドライン 【要約】
- 慢性膵炎(CP)は、従来、膵臓の不可逆的な炎症性疾患と定義され、外分泌機能障害と内分泌機能障害を様々な程度で引き起こすとされてきました。
- しかし近年、診断のパラダイムシフトが起こり、従来の臨床病理学的定義から脱却し、疾患初期における病理学的プロセスの早期診断と、疾患の自然経過を変えること、有害な疾患影響を最小限に抑えることを目的としたより包括的な症候群管理に焦点が当てられるようになりました。
- 現在最も受け入れられているCPの定義は、遺伝的、環境的、その他の危険因子を持つ個体において、膵実質への傷害やストレスに対する持続的な病理学的反応を発症する、膵臓の線維炎症性症候群です。
- CPの最も一般的な症状は腹痛であり、外分泌膵機能不全や糖尿病などの他の症状は、非常に変動する割合で発症します。
- CPの最も一般的な原因は、アルコールやタバコなどの毒素、遺伝的多型、急性膵炎の反復発作ですが、多くの患者では急性膵炎の病歴はありません。
- 診断は通常、断層撮影によって行われ、内視鏡的超音波検査や膵機能検査などは二次的な役割を果たします。
- 全膵摘出術はCPの唯一の既知の治療法ですが、患者の選択の難しさやこの介入に固有の合併症のために、通常は魅力的な選択肢ではありません。
- 本ガイドラインは、一般消化器科医のためのCPの診断と管理に関するエビデンスに基づいた実践的なアプローチを提供します。 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32022720
[quote_source]: Gardner TB, Adler DG, Forsmark CE, Sauer BG, Taylor JR and Whitcomb DC. “ACG Clinical Guideline: Chronic Pancreatitis.” The American journal of gastroenterology 115, no. 3 (2020): 322-339.
[title]: European Guideline on IgG4-related digestive disease – UEG and SGF evidence-based recommendations.
【要約】
- 本ガイドラインの目的は、成人および小児における免疫グロブリンG4(IgG4)関連消化器疾患の診断と治療について、エビデンスに基づいた推奨事項を提供することである。
- IgG4関連消化器疾患の診断には、組織学的検査、画像診断による臓器形態、血清学的検査、他の臓器への関与の有無の調査、およびグルココルチコイド治療への反応などを含む包括的な検査が必要である。
- 治療の適応は、閉塞性黄疸、腹痛、膵臓後部痛、およびIgG4関連胆管炎を含む膵臓以外の消化器臓器の関与を呈する症状のある患者である。
- グルココルチコイド治療は体重に基づいて行われ、寛解を誘導するために1か月間、1日あたり体重1kgあたり0.6~0.8mgの経口投与(プレドニゾン換算で通常30~40mg/日を初期投与量とする)を開始し、その後さらに2か月かけて減量する。
- 初期治療への反応は、臨床的、生化学的、形態学的マーカーを用いて2~4週目に評価する。
- 多臓器疾患または再発歴のある患者では、グルココルチコイドの維持療法を考慮する必要がある。
- 3か月以内に疾患活動性と負担に変化がない場合は、診断の見直しが必要である。
- 3か月の治療中に疾患が再発した場合は、免疫抑制薬を追加する必要がある。 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32552502
[quote_source]: Löhr JM, Beuers U, Vujasinovic M, Alvaro D, Frøkjær JB, Buttgereit F, Capurso G, Culver EL, de-Madaria E, Della-Torre E, Detlefsen S, Dominguez-Muñoz E, Czubkowski P, Ewald N, Frulloni L, Gubergrits N, Duman DG, Hackert T, Iglesias-Garcia J, Kartalis N, Laghi A, Lammert F, Lindgren F, Okhlobystin A, Oracz G, Parniczky A, Mucelli RMP, Rebours V, Rosendahl J, Schleinitz N, Schneider A, van Bommel EF, Verbeke CS, Vullierme MP, Witt H and UEG guideline working group. “European Guideline on IgG4-related digestive disease – UEG and SGF evidence-based recommendations.” United European gastroenterology journal 8, no. 6 (2020): 637-666.
[title]: Updated International Consensus Diagnostic Criteria for Eosinophilic Esophagitis: Proceedings of the AGREE Conference.
好酸球性食道炎の国際的診断基準に関する最新の合意:AGREE会議の報告 【要約】
- 過去10年間、好酸球性食道炎(EoE)の診断戦略におけるプロトンポンプ阻害剤(PPI)の使用に関して、臨床経験と研究から懸念が提起されていた。
- 本研究は、EoEが疑われる小児と成人の評価と治療におけるPPIの使用を明確化し、EoE診断のための最新の国際的合意基準を策定することを目的とした。
- 胃腸科、アレルギー科、病理学の専門分野を代表する14カ国の小児科医と成人科医、研究者からなるコンセンサス会議が開催され、文献と臨床経験をレビューした。
- PPIが小児、青年、成人における食道好酸球数を減少させるという十分な証拠が得られ、その治療効果を説明する可能性のあるいくつかのメカニズムが示唆された。
- これらの知見に基づき、PPI試験の要件を削除したEoEの更新された診断アルゴリズムが開発された。
- 食道機能障害の症状と、食道生検における高倍率視野あたり少なくとも15個の好酸球(または約60個/mm²)が存在し、食道好酸球症を引き起こす可能性のある、または寄与する可能性のある非EoE疾患の包括的な評価を行った後、EoEと診断されるべきである。
- PPIは、EoEに起因する可能性のある食道好酸球症の治療薬として分類される方が適切であり、診断基準としては適切ではないことが示唆された。この変更を反映したEoEに関する最新の合意基準が策定された。 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30009819
[quote_source]: Dellon ES, Liacouras CA, Molina-Infante J, Furuta GT, Spergel JM, Zevit N, Spechler SJ, Attwood SE, Straumann A, Aceves SS, Alexander JA, Atkins D, Arva NC, Blanchard C, Bonis PA, Book WM, Capocelli KE, Chehade M, Cheng E, Collins MH, Davis CM, Dias JA, Di Lorenzo C, Dohil R, Dupont C, Falk GW, Ferreira CT, Fox A, Gonsalves NP, Gupta SK, Katzka DA, Kinoshita Y, Menard-Katcher C, Kodroff E, Metz DC, Miehlke S, Muir AB, Mukkada VA, Murch S, Nurko S, Ohtsuka Y, Orel R, Papadopoulou A, Peterson KA, Philpott H, Putnam PE, Richter JE, Rosen R, Rothenberg ME, Schoepfer A, Scott MM, Shah N, Sheikh J, Souza RF, Strobel MJ, Talley NJ, Vaezi MF, Vandenplas Y, Vieira MC, Walker MM, Wechsler JB, Wershil BK, Wen T, Yang GY, Hirano I and Bredenoord AJ. “Updated International Consensus Diagnostic Criteria for Eosinophilic Esophagitis: Proceedings of the AGREE Conference.” Gastroenterology 155, no. 4 (2018): 1022-1033.e10.
[title]: The 1st EoETALY Consensus on the Diagnosis and Management of Eosinophilic Esophagitis – Definition, Clinical Presentation and Diagnosis.
好酸球性食道炎(EoE)の診断と治療に関するEoETALYコンセンサス:定義、臨床症状、診断 【要約】
- 好酸球性食道炎(EoE)は、最も一般的な好酸球性胃腸疾患であり、慢性的な2型免疫応答を介した食道の炎症性疾患である。
- イタリアのEoE専門家(EoETALYコンセンサスグループ)が、デルファイ法を用いてEoE患者の管理に関する最新のコンセンサスステートメントを作成した。これは、最近のエビデンスを踏まえ、イタリア消化器病学会(SIGE)の以前の報告書を更新するものである。
- 推奨事項のエビデンスの強度と質の評価には、GRADE基準が用いられた。
- ガイドラインは2つの文書に分かれており、パート1には定義、疫学、病因;臨床症状と自然経過;診断の3つの章が含まれ、パート2には治療;モニタリングとフォローアップの2つの章が含まれる。
- イタリア消化器病学会(SIGE)、イタリア神経胃腸運動学会(SINGEM)、イタリアアレルギー・喘息・臨床免疫学会(SIAAIC)の3つのイタリア国立学会の承認を得ている。
- イタリア好酸球性食道炎患者会(ESEO Italia)のメンバーも参加している。 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38423918
[quote_source]: de Bortoli N, Visaggi P, Penagini R, Annibale B, Baiano Svizzero F, Barbara G, Bartolo O, Battaglia E, Di Sabatino A, De Angelis P, Docimo L, Frazzoni M, Furnari M, Iori A, Iovino P, Lenti MV, Marabotto E, Marasco G, Mauro A, Oliva S, Pellegatta G, Pesce M, Privitera AC, Puxeddu I, Racca F, Ribolsi M, Ridolo E, Russo S, Sarnelli G, Tolone S, Zentilin P, Zingone F, Barberio B, Ghisa M and Savarino EV. “The 1st EoETALY Consensus on the Diagnosis and Management of Eosinophilic Esophagitis – Definition, Clinical Presentation and Diagnosis.” Digestive and liver disease : official journal of the Italian Society of Gastroenterology and the Italian Association for the Study of the Liver 56, no. 6 (2024): 951-963.
[title]: Allergic Diseases and Mental Health.
アレルギー疾患と精神健康 【要約】
- アレルギー疾患を持つ患者において、神経精神症状がしばしば併存するということは、古くから認識されている。
- この関連性のメカニズムは、疾患や患者集団によって異なり、神経炎症や、疾患症状とその管理に伴う社会的な影響が含まれる可能性がある。
- 本論文では、アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎、喘息、声帯機能障害、蕁麻疹、食物アレルギーと精神健康との関連について概観している。
- 多くの不明な点が残っており、特にアレルギー疾患の神経免疫軸における病態生理学的メカニズムと薬物相互作用について、さらなる研究が必要である。
- 患者健康質問票(PHQ)や全般性不安障害スクリーニングツールなどのツールを用いた精神的健康課題への予防的なスクリーニングは、臨床医がさらなる精神医学的評価と支援を必要とする患者を特定するのに役立つ。
- 症状スクリーニングツールは便利であるが、感受性と特異性にばらつきがあるため限界があり、そのため医療従事者は他の精神的健康上の「危険信号」にも注意する必要がある。
- 最終的に、アレルギー疾患と精神健康の関連性を理解することは、臨床医が患者の多様な身体的および精神的健康ニーズを予測し、対応することを可能にする。 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38851487
[quote_source]: Conway AE, Verdi M, Kartha N, Maddukuri C, Anagnostou A, Abrams EM, Bansal P, Bukstein D, Nowak-Wegrzyn A, Oppenheimer J, Madan JC, Garnaat SL, Bernstein JA and Shaker MS. “Allergic Diseases and Mental Health.” The journal of allergy and clinical immunology. In practice 12, no. 9 (2024): 2298-2309.


