「だるい」「疲れが取れない」…その倦怠感、もしかしたら病気のサインかもしれません。実は、倦怠感は貧血や甲状腺機能低下症といった身体的な原因から、うつ病などの精神的な原因、そして睡眠不足といった生活習慣まで、実に様々な要因で引き起こされるのです。さらに、がん治療による副作用で倦怠感が続くケースもあることをご存知でしょうか?2020年の研究では、がん関連疲労は診断不足、治療不足の現状があると報告されています。この記事では、倦怠感が続く原因を4つのカテゴリーに分け、具体的な病気や症状、最新の研究データまで詳しく解説。さらに、倦怠感を和らげるためのセルフケアについてもご紹介しています。ご自身の状況と照らし合わせながら、ぜひチェックしてみてください。
【この記事の著者のご紹介】
みなさんお待たせしました。専門医がお答えシリーズです!
お待たせし過ぎたかもしれませんし、誰もお待ちではないかもしれません。
内視鏡といえば天白橋。内科もやっぱり天白橋。天白橋内科内視鏡クリニックの院長野田です。
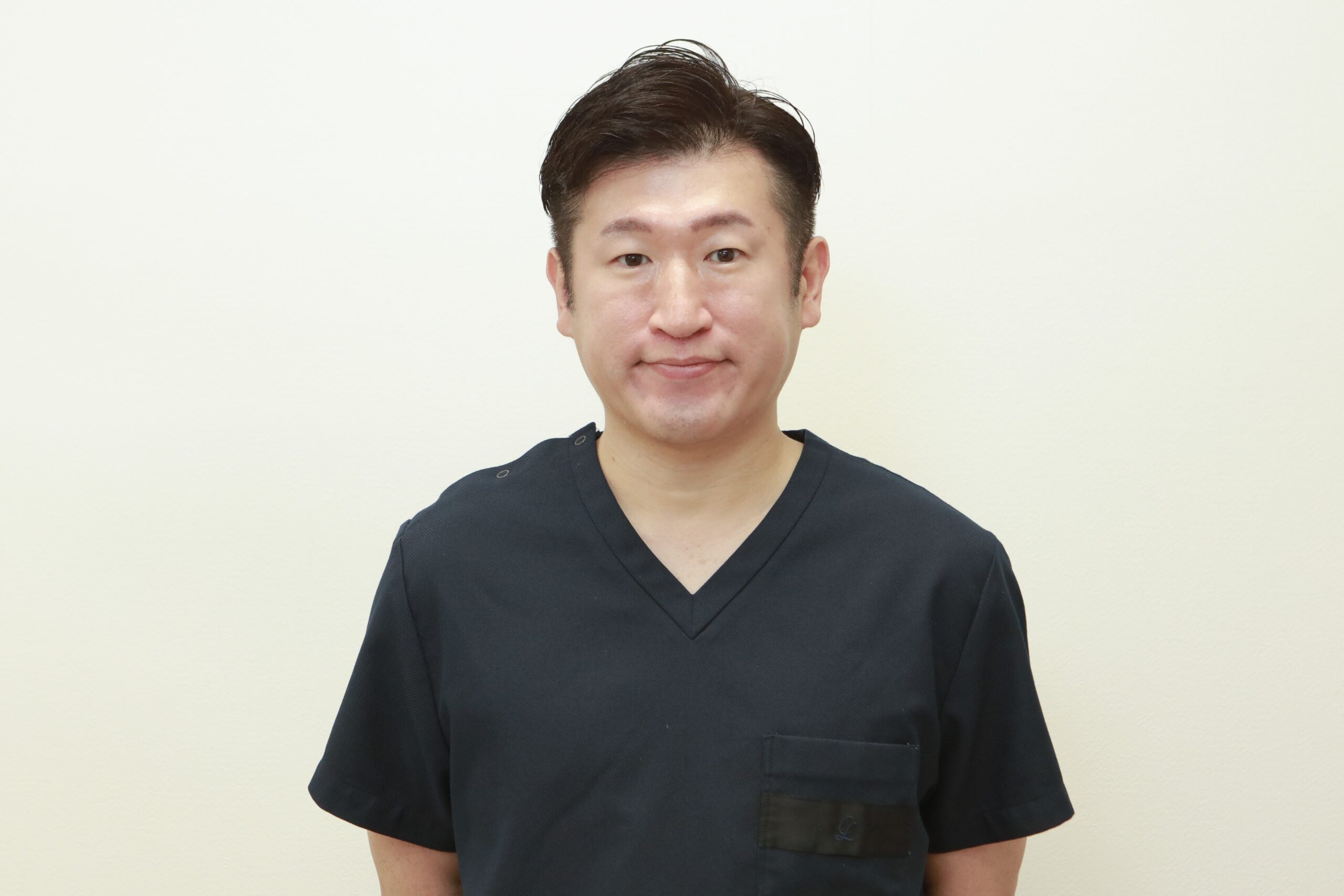
https://tenpakubashi-cl.com/staff/
https://tenpakubashi-cl.jbplt.jp/
目次
倦怠感が続く原因をチェック!4つの原因と危険なサイン
「だるくて何もやる気が起きない」「疲れがなかなか取れない…」というのは、多くの人が経験する症状です。しかし、その倦怠感が長く続くと、日常生活にも支障が出てしまい、不安になりますよね。
当院は内科・内視鏡クリニックとして、地域のかかりつけ医を目指しています。内視鏡検査はもちろんのこと、風邪のような一般的な症状から、今回のような「なんとなくだるい」といった漠然とした訴えまで、幅広く対応していますので、どうぞお気軽にご相談ください。
倦怠感は、実に様々な原因で起こります。原因を特定するためには、いくつかのステップを踏む必要があります。ここでは、倦怠感が続く原因を4つのカテゴリーに分けて詳しく解説していきます。ご自身の状況と照らし合わせて、思い当たる節がないか確認してみてください。
身体的な原因:貧血、甲状腺機能低下症、慢性疲労症候群など
倦怠感は、身体の病気のサインであることが少なくありません。
例えば、貧血は、体内の赤血球が不足することで、全身に酸素が十分に行き渡らなくなる状態です。酸素不足になると、全身の細胞がエネルギー不足に陥り、疲れやすくなります。貧血は特に女性に多く、隠れ貧血といって自覚症状がない場合もあります。血液検査で簡単に診断できますので、気になる方は一度検査を受けてみることをお勧めします。
また、甲状腺機能低下症は、甲状腺ホルモンの分泌量が低下する病気です。甲状腺ホルモンは、全身の代謝を調整する重要な役割を担っています。そのため、ホルモンが不足すると代謝が低下し、倦怠感だけでなく、むくみや便秘といった症状も現れます。
慢性疲労症候群は、原因不明の強い倦怠感が6ヶ月以上続き、日常生活に支障をきたす病気です。思考力の低下や睡眠障害などを伴うこともあります。
その他にも、糖尿病、心不全、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、電解質異常、急性肝炎なども倦怠感を引き起こすことがあります。
このように、倦怠感は様々な病気が隠れている可能性があります。当院では、血液検査をはじめ、患者様の状態に合わせて適切な検査を行い、原因を特定いたします。
精神的な原因:うつ病、不安障害、適応障害など
身体の病気だけでなく、心の不調が倦怠感につながることも珍しくありません。
例えば、うつ病は、気分の落ち込みや興味・喜びの喪失、食欲不振、不眠など、様々な症状が現れる病気です。倦怠感は、うつ病の代表的な症状の一つです。
強い不安や恐怖感に襲われる不安障害も、心身ともに疲弊し、倦怠感を引き起こすことがあります。
また、環境の変化やストレスにうまく適応できない適応障害でも、倦怠感が症状の一つとして現れることがあります。
精神的な原因による倦怠感は、自分自身で状態を把握することが難しい場合もあります。一人で抱え込まず、医療機関に相談することが大切です。
生活習慣:睡眠不足、栄養不足、過労など
もしかしたら、毎日の生活の中に倦怠感の原因が隠れているかもしれません。
睡眠不足は、心身の疲労回復を妨げ、倦怠感を招きます。寝る直前までスマートフォンを操作したり、寝る時間がバラバラだったりすると、睡眠の質が低下しやすくなります。毎日同じ時間に寝起きし、寝る前はリラックスする時間を作るなど、睡眠の質を高める工夫をしてみましょう。
栄養不足も倦怠感の原因となります。特に、ビタミンB群や鉄分は、エネルギー産生に重要な役割を果たしています。インスタント食品やファーストフードばかり食べていると、これらの栄養素が不足しがちです。バランスの取れた食事を心がけ、不足している栄養素はサプリメントなどで補うと良いでしょう。
また、仕事や家事などで身体を酷使し続けると、慢性的な疲労状態に陥り、倦怠感が続きます。疲れている時は、しっかりと休息を取るように心がけましょう。
がん関連疲労:がん治療による副作用
がん関連疲労(CRF)は、がん治療中および治療後のがん生存者において、大きな問題となっています。がん治療は身体に大きな負担をかけるため、倦怠感が現れやすいです。
がんによる身体への負担、痛み、精神的なストレス、栄養状態の悪化、貧血、ホルモンバランスの乱れなど、CRFの原因は多岐にわたると考えられており、現在も研究が進められています。例えば、2020年に発表された論文(Thong MSY, et al., 2020)では、CRFの原因と治療選択肢について包括的にレビューされています。この論文によれば、CRFは診断不足、治療不足の現状があり、標準的な治療法は確立されていないとされています。
倦怠感はよくある症状ですが、放置すると日常生活に大きな影響を及ぼす可能性があります。がん治療を受けている方はもちろん、治療後も倦怠感が続く場合は、医療機関に相談することをお勧めします。当院では、患者様一人ひとりの状況を丁寧に伺い、適切なサポートをさせていただきます。
倦怠感の適切な治療法3選|天白橋内科内視鏡クリニック
「最近、どうも疲れが抜けない…」「だるくてやる気が出ない…」そんな倦怠感に悩まされていませんか?
実は、その倦怠感は一時的な疲労だけでなく、何らかの病気が隠れているサインかもしれません。
当院は、内科・内視鏡クリニックとして地域医療に貢献しており、風邪などの一般的な症状から、内視鏡検査、そして美容医療まで、幅広く診療を行っています。
「なんとなくだるい」といった漠然とした訴えにも、きちんと耳を傾け、患者様一人ひとりに寄り添った診療を心がけていますので、どうぞお気軽にご相談ください。
早期発見・早期治療が大切です。倦怠感を放置することで、日常生活に大きな支障をきたす可能性もあるため、まずはご自身の状態を把握し、適切な対応をすることが重要です。
血液検査、尿検査、画像検査など
倦怠感の原因を特定するためには、まず丁寧な問診と診察を行います。
その上で、血液検査、尿検査、画像検査など、患者様の状態に合わせた検査を実施します。
血液検査では、貧血、炎症反応、肝臓や腎臓の機能、ホルモンバランス、血糖値、電解質異常など、様々な項目をチェックします。
例えば、貧血は、体内に酸素を運ぶ赤血球が不足することで起こり、倦怠感をはじめ、動悸やめまいなどの症状が現れます。
また、甲状腺ホルモンは全身の代謝を調整する重要な役割を担っており、甲状腺機能の異常も倦怠感の原因となるため、甲状腺機能検査も行います。
尿検査では、腎臓の機能や尿路感染症の有無などを確認します。
さらに、必要に応じて心電図、胸部レントゲン、腹部エコー、CT、MRIなどの画像検査を行い、心臓、肺、消化器などの臓器に異常がないかを調べます。
がん関連疲労の可能性も考慮し、患者様の状態に合わせて適切な検査を選択します。
倦怠感の原因に合わせた薬物療法、生活指導など
検査結果に基づき、倦怠感の原因を特定し、その原因に合わせた治療を行います。
例えば、貧血が原因の場合は、鉄剤の処方や鉄分の多い食品を積極的に摂るよう食生活の指導を行います。
甲状腺機能異常が原因の場合は、甲状腺ホルモン剤の投与を行います。
感染症が原因の場合は、抗菌薬や抗ウイルス薬を処方します。
また、うつ病や不安障害などの精神的な原因が考えられる場合は、抗うつ薬や抗不安薬などを用いた薬物療法や、カウンセリングなどの精神療法を行います。
さらに、生活習慣の改善も倦怠感の治療には非常に重要です。
十分な睡眠、バランスの良い食事、適度な運動、ストレスマネジメントなど、患者様一人ひとりに合った生活指導を行います。
天白橋内科内視鏡クリニックの特徴とアクセス情報
天白橋内科内視鏡クリニックは、名古屋市営地下鉄鶴舞線「原駅」より徒歩2分の場所に位置し、近隣には提携駐車場もございますので、お車でも公共交通機関でも通院しやすい環境です。
当クリニックは、内視鏡検査に精通した内科専門医が、風邪などの一般的な症状から消化器疾患、生活習慣病、そしてがん関連疲労のような複雑な症状まで、幅広い疾患に対応いたします。
「なんとなくだるい」といった漠然とした倦怠感でお悩みの方も、どうぞお気軽にご相談ください。
患者様一人ひとりの症状に真摯に向き合い、丁寧な診察と分かりやすい説明を心がけております。
患者様の様々なニーズにお応えできるよう努めていますので、お気軽にご相談ください。
倦怠感を和らげる5つのセルフケア|日常生活の改善
「だるい」「疲れがとれない」…誰にでも経験のある倦怠感。一時的なものなら問題ありませんが、長く続く場合は、生活の質を大きく下げてしまうだけでなく、重大な病気のサインである可能性も否定できません。
当院は、内科・内視鏡クリニックとして、地域のかかりつけ医を目指しています。内視鏡検査はもちろんのこと、風邪のような一般的な症状から、「なんとなくだるい」といった漠然とした訴えまで、幅広く対応しています。
この章では、倦怠感を和らげるための5つのセルフケアの方法をご紹介します。今日からできる簡単なものばかりですので、ぜひ試してみてください。
睡眠の質を上げる:睡眠時間、睡眠環境
睡眠は、心身の疲労を回復させるための大切な時間です。質の良い睡眠をとることで、日中の活動に必要なエネルギーを蓄え、倦怠感を軽減することができます。
-
睡眠時間: 毎日同じ時間に寝起きすることで、体内時計が調整され、睡眠の質が向上します。理想的な睡眠時間は、個人差がありますが、一般的には7~8時間と言われています。6時間未満の睡眠が続くと、日中のパフォーマンス低下や倦怠感につながりやすくなります。逆に、9時間以上の睡眠も、倦怠感を引き起こすことがあるため、注意が必要です。
-
睡眠環境: 寝室の温度や湿度、明るさ、音など、睡眠環境を整えることも重要です。室温は20~23度、湿度は50~60%が最適と言われています。また、寝る前は明るい光を避け、リラックスできる環境を作るようにしましょう。スマートフォンやパソコンの画面から出るブルーライトは、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を抑制するため、寝る直前まで使用するのは避けましょう。
バランスの取れた食事:栄養バランス、水分摂取
食生活の乱れは、エネルギー不足や栄養不足を招き、倦怠感につながることがあります。バランスの良い食事を心がけることで、身体に必要な栄養素を補給し、倦怠感を軽減することができます。
-
栄養バランス: 炭水化物、タンパク質、脂質の三大栄養素をバランスよく摂取することはもちろん、ビタミンやミネラルも重要です。特に、ビタミンB群はエネルギー代謝に不可欠な栄養素であり、不足すると倦怠感を引き起こす可能性があります。豚肉、レバー、卵、牛乳、大豆製品などに多く含まれていますので、意識して摂取するようにしましょう。
-
水分摂取: 体内の水分が不足すると、血液の循環が悪くなり、酸素や栄養素が全身に行き渡らなくなります。その結果、倦怠感や疲労感が増強することがあります。のどの渇きを感じる前に、こまめに水分を補給するように心がけましょう。1日に必要な水分量は、約1.5~2リットルと言われています。
適度な運動:ウォーキング、ストレッチ
適度な運動は、血行を促進し、筋肉の緊張をほぐす効果があります。また、運動によって気分転換になり、ストレス軽減にもつながります。結果として、倦怠感の改善にも役立ちます。
-
ウォーキング: ウォーキングは、特別な道具や場所を必要とせず、手軽に始めることができる運動です。1日30分程度、自分のペースで歩くことを習慣づけてみましょう。
-
ストレッチ: ストレッチは、筋肉の柔軟性を高め、血行を促進する効果があります。朝起きた時や、お風呂上がりなど、毎日続けることで、身体の緊張をほぐし、倦怠感を軽減することができます。
休息:リラックス、ストレス軽減
過剰なストレスは、自律神経のバランスを崩し、倦怠感を悪化させる要因となります。意識的に休息を取り、リラックスする時間を作ることで、ストレスを軽減し、心身のバランスを整えましょう。
-
リラックス: 好きな音楽を聴いたり、アロマを焚いたり、読書をしたりなど、自分がリラックスできる方法を見つけましょう。ぬるめのお風呂にゆっくり浸かるのも効果的です。
-
ストレス軽減: ストレスの原因を特定し、可能な範囲で対処することも重要です。例えば、人間関係のストレスが原因であれば、信頼できる人に相談したり、距離を置くなど、自分を守るための行動をとりましょう。
周囲のサポート:家族、友人、医療従事者
倦怠感が長引く場合は、一人で抱え込まず、周囲のサポートを求めることが大切です。家族や友人に話を聞いてもらったり、医療従事者に相談することで、心身の負担を軽減し、適切な対応策を見つけることができます。
-
家族・友人: 家族や友人に自分の気持ちを伝えることで、精神的な支えを得ることができます。「つらい」「しんどい」と素直に伝えることで、気持ちが楽になることもあります。
-
医療従事者: 倦怠感の原因が特定できない場合や、セルフケアで改善しない場合は、医療機関を受診しましょう。医師は、問診、診察、血液検査などを通して、倦怠感の原因を探り、適切な治療法を提案します。がん治療中や治療後の倦怠感は、診断や治療が不十分なケースもあるため、医療機関への相談は特に重要です。
当院では、内科専門医が、倦怠感の原因を丁寧に調べ、患者様一人ひとりに合った治療法をご提案いたします。どうぞお気軽にご相談ください。
まとめ
倦怠感が続く原因は、身体的な病気、精神的な不調、生活習慣の乱れ、がん治療の副作用など様々です。もしかしたら、これらの原因が複雑に絡み合っているかもしれません。
重要なのは、倦怠感を「ただの疲れ」と安易に片付けず、ご自身の状態をしっかり把握することです。
まずは、生活習慣を見直してみましょう。睡眠、食事、運動、休息は、健康な毎日を送る上で基本となるものです。
それでも倦怠感が改善しない場合は、ためらわず医療機関に相談しましょう。
当院では、患者様一人ひとりの状況を丁寧に伺い、適切な検査と治療を行います。
「なんとなくだるい」といった漠然としたお悩みでも構いません。どうぞお気軽にご相談ください。
全ては患者さんの「もっと早く治療しとけばよかった・・・」を無くしたいから。
詳しくは当院のホームページ(←こちらをクリック)からどうぞ。



令和7年4月11日
天白橋内科内視鏡クリニック 野田久嗣
・医学博士
・日本内科学会認定内科医
・日本消化器病学会消化器病専門医
・日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医
参考文献
- Thong MSY, van Noorden CJF, Steindorf K, Arndt V. Cancer-Related Fatigue: Causes and Current Treatment Options. Current treatment options in oncology 21, no. 2 (2020): 17.
追加情報
[title]: Cancer-Related Fatigue: Causes and Current Treatment Options.,
がん関連疲労:原因と現在の治療選択肢
【要約】
がん治療中および治療後のがん生存者の相当数において、がん関連疲労(CRF)は大きな問題となっている。
しかしながら、CRFは診断不足、治療不足である。
CRFに対する介入は存在するものの、標準治療法はない。
現状のエビデンスレベルに基づくと、運動療法は、治療中および治療後のCRFの予防または改善において最も効果的であると考えられる。
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32025928,
[quote_source]: Thong MSY, van Noorden CJF, Steindorf K and Arndt V. “Cancer-Related Fatigue: Causes and Current Treatment Options.” Current treatment options in oncology 21, no. 2 (2020): 17.


