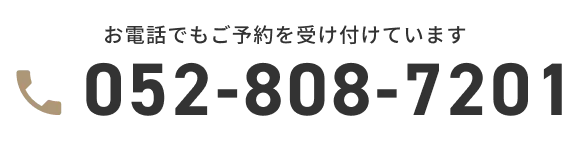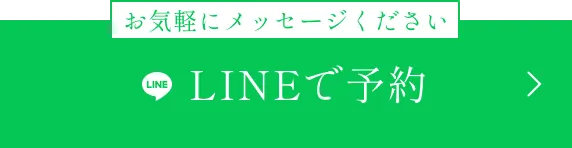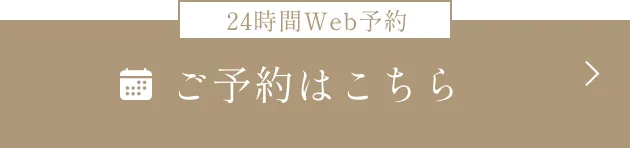微熱が続く…それ、実は危険信号かもしれません。ただの風邪と安易に考えていませんか? 実は微熱は、風邪などのありふれた病気から、甲状腺の病気、そして、まれではありますが、がんのような深刻な病気が隠れている可能性があるのです。もしかしたら、あなたの体の中で、何か重大な異変が起きているかもしれません。この記事では、微熱が続く原因を内科医が詳しく解説します。具体的な病気の種類から、その症状、そして対処法まで、微熱の謎を徹底的に解き明かします。ご自身の健康を守るためにも、ぜひ最後まで読んでみてください。
【この記事の著者のご紹介】
みなさんお待たせしました。専門医がお答えシリーズです!
お待たせし過ぎたかもしれませんし、誰もお待ちではないかもしれません。
内視鏡といえば天白橋。内科もやっぱり天白橋。天白橋内科内視鏡クリニックの院長野田です。
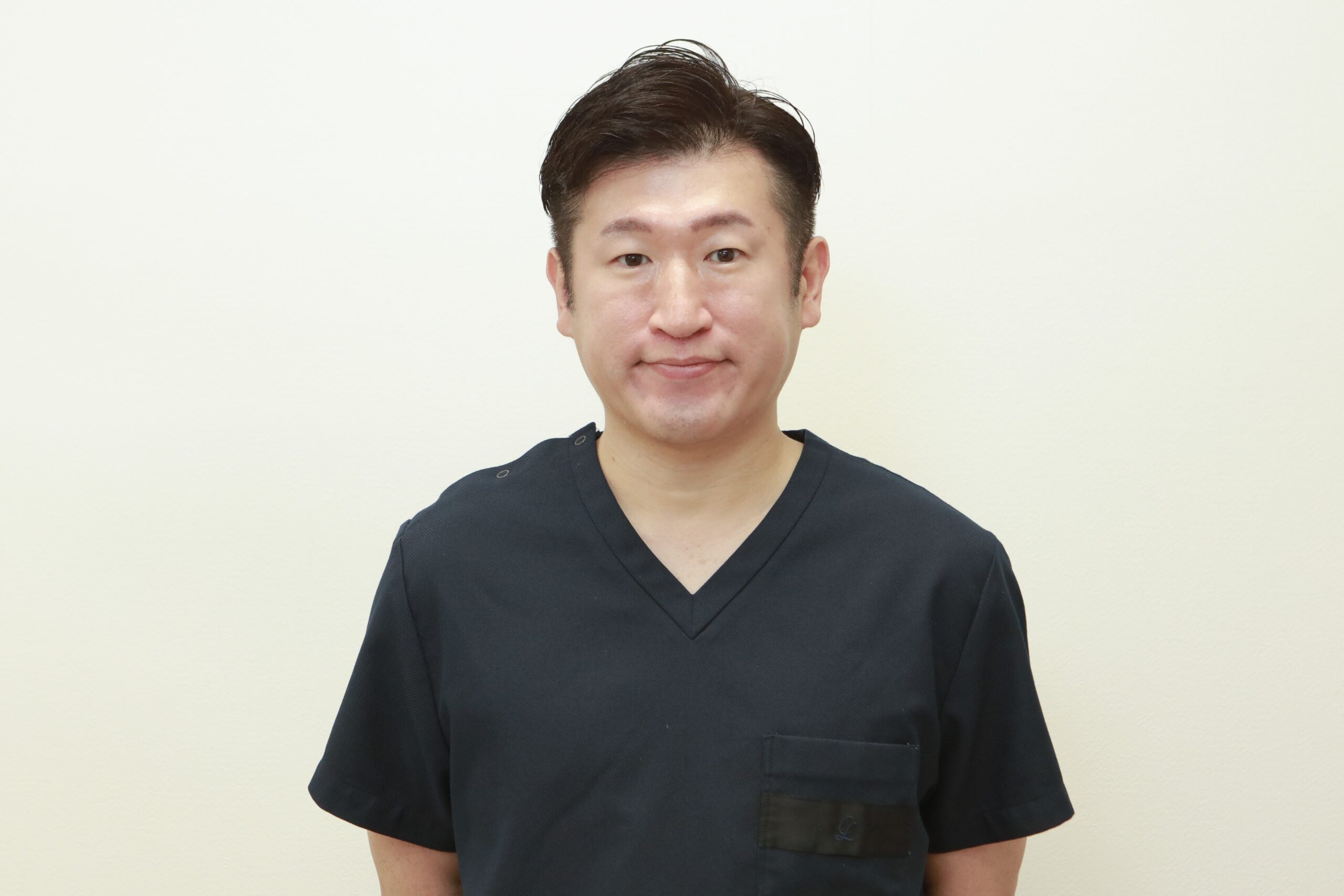
https://tenpakubashi-cl.com/staff/
https://tenpakubashi-cl.jbplt.jp/
微熱が続く原因を特定する5つのポイント
微熱が続くと、体も心も重く、不安な気持ちになりますよね。ただの風邪だろうかと軽く考えがちですが、実は微熱は様々な病気のサインである可能性があります。風邪のようなありふれた病気から、甲状腺の病気、そしてまれではありますが、がんのような深刻な病気が隠れているケースもあるのです。
まず大切なのは、ご自身の平熱を知ることです。一般的には37℃未満と言われていますが、人によって、また1日の時間帯によっても体温は変動します。普段から体温を測る習慣を身につけて、自分の平熱を把握しておきましょう。また、微熱以外に、咳や鼻水、だるさなど、何かいつもと違う症状がないかにも注意を払うことが大切です。
当院は内科・内視鏡クリニックとして、地域のかかりつけ医を目指しています。発熱外来のような一次救急から、専門性の高い内視鏡検査、そして医療アートメイクやエクソソーム点滴療法まで、幅広く対応しています。どんな些細なことでも構いません。お気軽にご相談ください。
感染症:風邪、インフルエンザ、コロナウイルスなど
微熱の原因として最も多いのは、風邪などの感染症です。風邪の原因のほとんどはウイルス感染で、鼻水やくしゃみ、のどの痛み、発熱、頭痛など、様々な症状が現れます。多くの場合、1週間から10日ほどで自然に治りますが、長引く場合は他の病気が隠れている可能性も考えられます。自己判断せずに、医療機関を受診しましょう。
例えば、新型コロナウイルス感染症では、発熱、咳などの軽い風邪のような症状から、息苦しさや強いだるさ、高熱といった重症化するケースまで様々です。また、結核菌への感染が原因となる肺結核も、初期症状として微熱が現れることがあります。咳や痰、微熱、倦怠感、体重減少といった症状が2週間以上続く場合は、肺結核の可能性も考慮する必要があります。結核は感染しても発症しない人が約9割ですが、高齢者や免疫力が低下している人は発症しやすいので注意が必要です。
当院では、患者様一人ひとりに合わせた丁寧な診察・治療を心がけております。
ご不明点やご不安な点がありましたら、遠慮なくスタッフにお尋ねください。
患者様の健康と快適な生活サポートするため、全力でお手伝いさせていただきます。

炎症性疾患:膠原病、血管炎など
膠原病や血管炎といった炎症性疾患も、微熱の原因となることがあります。これらの病気は、自分の免疫システムが誤って自分の体を攻撃してしまう自己免疫疾患の一種です。全身の様々な臓器に炎症を引き起こし、微熱以外にも、関節の痛みや発疹、倦怠感など、多様な症状が現れます。
例えば、全身性エリテマトーデスでは関節痛や皮疹、倦怠感などの症状に加えて、日光に当たると皮膚が赤くなる日光過敏症や、にきびが増えるといった症状が現れることもあります。また、巨細胞性動脈炎(側頭動脈炎)では、激しい頭痛や手足の痛み、顎の痛みなどを伴うことがあります。微熱が続くだけでなく、これらの症状がある場合は、膠原病や血管炎の可能性も考えて、医療機関を受診することが大切です。
悪性腫瘍:白血病、リンパ腫など
悪性腫瘍、いわゆるがんも、微熱の原因となることがあります。白血病やリンパ腫といった血液のがんでは、初期症状として微熱が現れることがあります。その他のがんでも、がん細胞が増殖する過程で炎症反応が起こり、微熱が生じることがあります。
白血病では、微熱以外にも、出血しやすくなったり、あざができやすくなったり、貧血の症状が現れることがあります。悪性リンパ腫では、リンパ節が腫れたり、寝汗をかいたり、体重が減少するといった症状が現れることがあります。また、膵臓がん、肝臓がん、胆嚢がんなど消化器系のがんでも微熱や倦怠感といった症状が現れることがあり、これらの症状だけでは発見が遅れてしまうケースも少なくありません。
甲状腺機能亢進症
甲状腺機能亢進症は、甲状腺ホルモンが過剰に分泌される病気です。甲状腺ホルモンは、体の代謝を調節する重要なホルモンですが、過剰に分泌されると、動悸や息切れ、発汗、微熱などの症状が現れます。当院では、血液検査によって甲状腺ホルモンの値を測定し、甲状腺機能亢進症の診断が可能です。
薬剤性発熱
薬剤性発熱とは、特定の薬を服用した後に発熱が起こる現象です。抗生物質や抗けいれん薬など、様々な薬が原因となる可能性があります。また、抗がん剤治療でがん細胞が破壊される際にも発熱が起こることがあります。薬剤性発熱は、原因となった薬剤の使用を中止することで改善することがほとんどですが、自己判断で薬を中断するのは危険です。必ず医師に相談してください。
生後8日から60日齢の赤ちゃんが38℃以上の発熱をしている場合、見た目には元気そうでも、様々な疾患が隠れている可能性があり、注意深い観察と検査が必要です。この年齢の赤ちゃんは免疫システムが未発達なため、重篤な感染症のリスクが高く、迅速な対応が重要となります。
天白橋内科内視鏡クリニックでは、内科全般の診療に対応しており、微熱の原因を特定するための様々な検査が可能です。微熱が続く、原因がわからないなど、少しでも気になることがあれば、お気軽にご相談ください。
微熱に伴う症状と対処法
微熱が続くと、体も心も重く、不安な気持ちになりますよね。だるさや食欲不振など、様々な不調が現れ、日常生活にも支障をきたすことがあります。微熱は、風邪などの比較的軽い病気から、より深刻な病気が隠れているサインである場合もあります。
当院は、地域のかかりつけ医として、風邪などの一般的な内科疾患から、専門性の高い内視鏡検査まで、幅広く診療を行っています。微熱が続くなど、気になる症状がありましたら、些細なことでもお気軽にご相談ください。
全身倦怠感:休息と栄養補給
微熱に伴い、全身倦怠感、いわゆる「だるさ」を感じる方は多いのではないでしょうか。まるで鉛のように体が重く、何もする気力が起きない、といった状態に陥ることもあります。
この倦怠感は、体内で炎症反応が起こっているサインである可能性があります。例えば、風邪などの感染症にかかると、私たちの体はウイルスや細菌と戦うために免疫システムを活性化させます。この過程で、炎症性サイトカインと呼ばれる物質が放出され、倦怠感などの症状を引き起こすのです。
倦怠感を和らげるためには、まず十分な休息が必要です。体を休ませることで、免疫システムの回復を促し、炎症反応を抑えることができます。睡眠時間をしっかり確保し、日中は無理せず体を休めるようにしましょう。
また、栄養補給も重要です。バランスの良い食事を摂ることで、免疫システムに必要な栄養素を供給し、体の抵抗力を高めることができます。特に、たんぱく質、ビタミン、ミネラルは、免疫細胞の働きを維持するために不可欠です。消化の良いものを少量ずつ、こまめに摂取するように心がけましょう。
安静にしていても倦怠感が改善しない、あるいは悪化する場合は、他の病気が隠れている可能性があります。自己判断せずに、医療機関を受診しましょう。
食欲不振:消化の良いものを少量ずつ摂取
微熱が出ているときは、食欲が落ちてしまうことがよくあります。これは、体内で炎症反応が起こっている影響で、消化機能が低下していることが原因の一つとして考えられます。
食欲不振が続くと、栄養不足に陥り、免疫力が低下する可能性があります。そのため、無理にたくさん食べようとせず、消化の良いものを少量ずつ、こまめに摂取するようにしましょう。
おすすめは、おかゆ、うどん、スープ、ヨーグルト、果物など、胃腸に負担をかけにくい食べ物です。また、水分も不足しがちなので、こまめな水分補給を心がけましょう。水やスポーツドリンク、経口補水液などがおすすめです。
食欲不振が長引く場合は、脱水症状や栄養失調の危険性もありますので、早めに医療機関を受診し、適切なアドバイスを受けるようにしましょう。
頭痛:鎮痛剤の使用と冷却
微熱とともに頭痛が現れることもあります。ズキズキとした痛みや、頭が締め付けられるような感覚など、症状は様々です。
微熱による頭痛の原因は、炎症反応や脱水症状などが考えられます。炎症によって脳の血管が拡張し、神経を刺激することで頭痛が生じます。また、発汗によって体内の水分が失われると、脱水症状を引き起こし、頭痛を悪化させる可能性があります。
市販の鎮痛剤は、頭痛の症状を緩和するのに役立ちます。ただし、鎮痛剤の種類や服用量、服用方法などは、薬剤師や医師に相談するようにしましょう。
また、冷却シートや氷枕などで頭を冷やすことも効果的です。痛みが強い場合は、暗い静かな部屋で横になるなど、安静にすることも重要です。頭痛が長引いたり、痛みがひどい場合は、医療機関を受診しましょう。
発汗:水分補給
微熱時には、体が熱を放散しようと発汗することがあります。発汗は体温調節に重要な役割を果たしていますが、同時に体内の水分も失われてしまいます。
水分が不足すると、脱水症状を引き起こし、頭痛や倦怠感などの症状を悪化させる可能性があります。そのため、こまめな水分補給を心がけることが大切です。水やスポーツドリンク、経口補水液などがおすすめです。カフェインを含む飲み物は利尿作用があるため、避けた方が良いでしょう。
また、汗をかいた後は、清潔なタオルで体を拭き、衣服を着替えるようにしましょう。皮膚を清潔に保つことで、細菌感染のリスクを減らすことができます。発汗がひどい、または脱水症状の兆候がある場合は、医療機関を受診するようにしてください。
咳・鼻水:風邪薬の服用
咳や鼻水は、風邪などのウイルス感染症でよく見られる症状です。ウイルスが鼻や喉の粘膜に侵入し、炎症を起こすことで、咳や鼻水といった症状が現れます。
市販の風邪薬は、これらの症状を緩和するのに役立ちます。ただし、風邪薬には様々な種類がありますので、薬剤師や医師に相談して、自分に合った薬を選ぶことが大切です。
咳や鼻水は、ウイルスを体外に排出するための体の防御反応でもあります。しかし、咳や鼻水がひどい場合は、日常生活に支障をきたすこともあります。無理をせず、安静にすることが大切です。症状が長引く場合や、悪化する場合は、医療機関を受診するようにしましょう。特に、生後8日から60日齢の赤ちゃんが38℃以上の発熱をしている場合は、たとえ元気そうに見えても、迅速な対応が必要です。
天白橋内科内視鏡クリニックでは、患者さん一人ひとりの症状や状態に合わせて、適切な検査や治療を行っています。微熱が続く、原因がわからないなど、少しでも気になることがございましたら、お気軽にご相談ください。
天白橋内科内視鏡クリニックでの微熱の診断と治療
微熱が続くと、体も心も重く、不安な気持ちになりますよね。「ただの風邪かな?」と安易に考えてしまいがちですが、微熱は様々な病気のサインの可能性があるため、注意が必要です。
当院は内科・内視鏡クリニックとして、地域のかかりつけ医を目指しています。風邪などの一般的な内科疾患から専門性の高い内視鏡検査、発熱外来のような一次救急についてもご相談いただけますので、些細なことでもお気軽にご相談ください。
診察・問診:症状、既往歴、生活習慣など
微熱の原因を特定するために、まずは丁寧な問診を行います。問診では、患者さんの現在の症状、過去の病気やアレルギーの有無、現在服用している薬、そして日頃の生活習慣や食生活など、様々な情報をお伺いします。
具体的には、いつから微熱が続いているのか、体温はどの程度か、他に症状はあるか(咳、鼻水、倦怠感、頭痛、食欲不振、発汗、関節の痛み、筋肉の痛みなど)、過去に大きな病気をしたことがあるか、アレルギーはあるか、現在何か薬を服用しているか、普段の睡眠時間や食事内容、運動習慣、喫煙や飲酒の有無などをお聞きします。
これらの情報は、微熱の原因を探るための重要な手がかりとなります。例えば、微熱に加えて咳や鼻水がある場合は風邪などの感染症、関節の痛みがある場合は膠原病、体重減少や寝汗がある場合は悪性腫瘍といった具合です。
患者さんの中には、「こんなこと話しても意味がないのでは…」と遠慮される方もいらっしゃいますが、些細なことでも構いませんので、思いつくことは何でもお話しください。医師は、患者さんから提供された情報を総合的に判断し、微熱の原因を特定していきます。
血液検査:炎症反応、感染症の有無など
問診である程度の絞り込みを行った後は、血液検査を行います。血液検査では、炎症反応の有無や程度、感染症の有無、貧血の有無、肝機能や腎機能の状態、甲状腺ホルモンの値などを調べます。
炎症反応の指標となるCRPや白血球の数値が高い場合は、体内で炎症が起きていることを示唆します。感染症が疑われる場合は、血液中のウイルスや細菌を検出するための検査を追加で行うこともあります。
また、甲状腺ホルモンの値を調べることで、甲状腺機能亢進症の有無を判断できます。甲状腺機能亢進症は、甲状腺ホルモンが過剰に分泌されることで、代謝が上がり、微熱などの症状が現れる病気です。
画像検査:X線、CT、MRIなど
血液検査で異常が見つかった場合や、問診や血液検査だけでは原因を特定できない場合は、画像検査を行います。画像検査には、X線検査、CT検査、MRI検査などがあり、患者さんの症状や疑われる病気、年齢に応じて適切な検査方法を選択します。
例えば、咳や胸の痛みがある場合は胸部X線検査を行い、肺炎の有無などを調べます。腹部の痛みや消化器系の症状がある場合は、腹部CT検査や腹部超音波検査を行い、肝臓、膵臓、胆嚢などの状態を確認します。
画像検査によって、腫瘍や炎症、臓器の異常などを発見できる可能性があります。
必要な場合は専門医への紹介
微熱の原因が特定できない場合や、当院での治療が難しいと判断した場合は、適切な専門医をご紹介いたします。
例えば、膠原病が疑われる場合は膠原病内科、消化器系の病気が疑われる場合は消化器内科、血液疾患が疑われる場合は血液内科、内分泌系の病気が疑われる場合は内分泌内科など、患者さんの症状や状態に合わせて最適な専門医をご紹介しますので、ご安心ください。
まとめ
微熱が続く原因は、風邪などの感染症から、甲状腺の病気、そしてまれではありますが、がんのような深刻な病気まで様々です。
ご自身の平熱を知ること、微熱以外の症状にも注意を払い、少しでも異変を感じたら、自己判断せずに医療機関を受診することが大切です。
当院では、微熱の原因を特定するための問診、血液検査、画像検査など、様々な検査を行っています。微熱が続く、原因がわからない、など少しでも気になることがあれば、お気軽にご相談ください.
全ては患者さんの「もっと早く治療しとけばよかった・・・」を無くしたいから。
詳しくは当院のホームページ(←こちらをクリック)からどうぞ。



令和7年4月11日
天白橋内科内視鏡クリニック 野田久嗣
・医学博士
・日本内科学会認定内科医
・日本消化器病学会消化器病専門医
・日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医
参考文献
- Pantell RH, Roberts KB, Adams WG, Dreyer BP, Kuppermann N, O’Leary ST, Okechukwu K, Woods CR Jr and SUBCOMMITTEE ON FEBRILE INFANTS. Evaluation and Management of Well-Appearing Febrile Infants 8 to 60 Days Old. Pediatrics 148, no. 2 (2021).
追加情報
[title]: Evaluation and Management of Well-Appearing Febrile Infants 8 to 60 Days Old.,
生後8~60日齢の元気な発熱乳児の評価と管理
【要約】
本ガイドラインは、生後8~60日齢の元気な(外見上健康な)正期産児で、38.0℃以上の発熱を呈する乳児の評価と管理について述べている。除外基準についても言及している。
アメリカ保健医療研究品質庁によるエビデンスに基づくレビュー、広範かつ継続的な文献レビュー、そして研究者から提供された査読済み論文からの補足データに基づき、21個の重要な推奨事項が導き出された。
各推奨事項について、エビデンスの質とベネフィット・ハームの関係が評価され、推奨の強さがグレード分けされている。
適切な場合は、共有意思決定の一環として、両親の価値観と好みを考慮すべきである。
診断検査については、必要な検査数(Number Needed to Test: NNT)が算出され、抗菌薬投与については、必要な治療数(Number Needed to Treat: NNT)が提示されている。
生後8~21日齢、22~28日齢、29~60日齢の乳児に対する推奨事項をまとめた3つのアルゴリズムが提示されている。
本ガイドラインの推奨事項は、唯一の治療法を示すものではなく、医療の標準を意味するものでもない。個々の状況を考慮した変更が適切な場合もある。
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34281996,
[quote_source]: Pantell RH, Roberts KB, Adams WG, Dreyer BP, Kuppermann N, O’Leary ST, Okechukwu K, Woods CR Jr and SUBCOMMITTEE ON FEBRILE INFANTS. “Evaluation and Management of Well-Appearing Febrile Infants 8 to 60 Days Old.” Pediatrics 148, no. 2 (2021): .