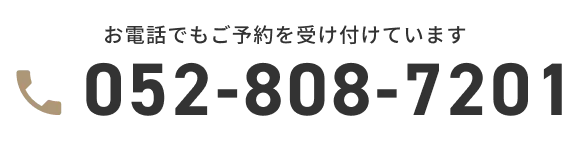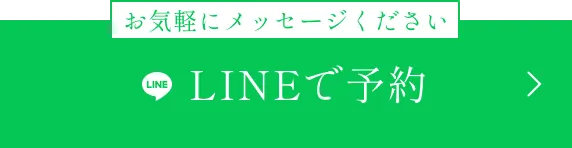新生活が始まり、期待とともに胸が高鳴る一方で、慣れない環境や人間関係、仕事のプレッシャーなど、様々なストレスに悩まされていませんか? 実は、こうしたストレスは体に様々な不調を引き起こす可能性があります。
厚生労働省の調査によると、現代人の約6割がストレスを感じていると回答しており、その影響は倦怠感や疲労感、頭痛、肩こり、食欲不振、胃腸の不調、気分の落ち込み、不安感、睡眠障害など、多岐にわたります。
この記事では、新生活のストレスで起こるよくある症状5選と、その対策、そしてストレスによる不調のメカニズムを詳しく解説します。
つらい症状を我慢し続けると、慢性的な不調につながる可能性も。
ご自身の状態を把握し、適切な対処法を知ることで、心身ともに健康な新生活を送りましょう。
【この記事の著者のご紹介】
みなさんお待たせしました。専門医がお答えシリーズです!
お待たせし過ぎたかもしれませんし、誰もお待ちではないかもしれません。
内視鏡といえば天白橋。内科もやっぱり天白橋。天白橋内科内視鏡クリニックの院長野田です。
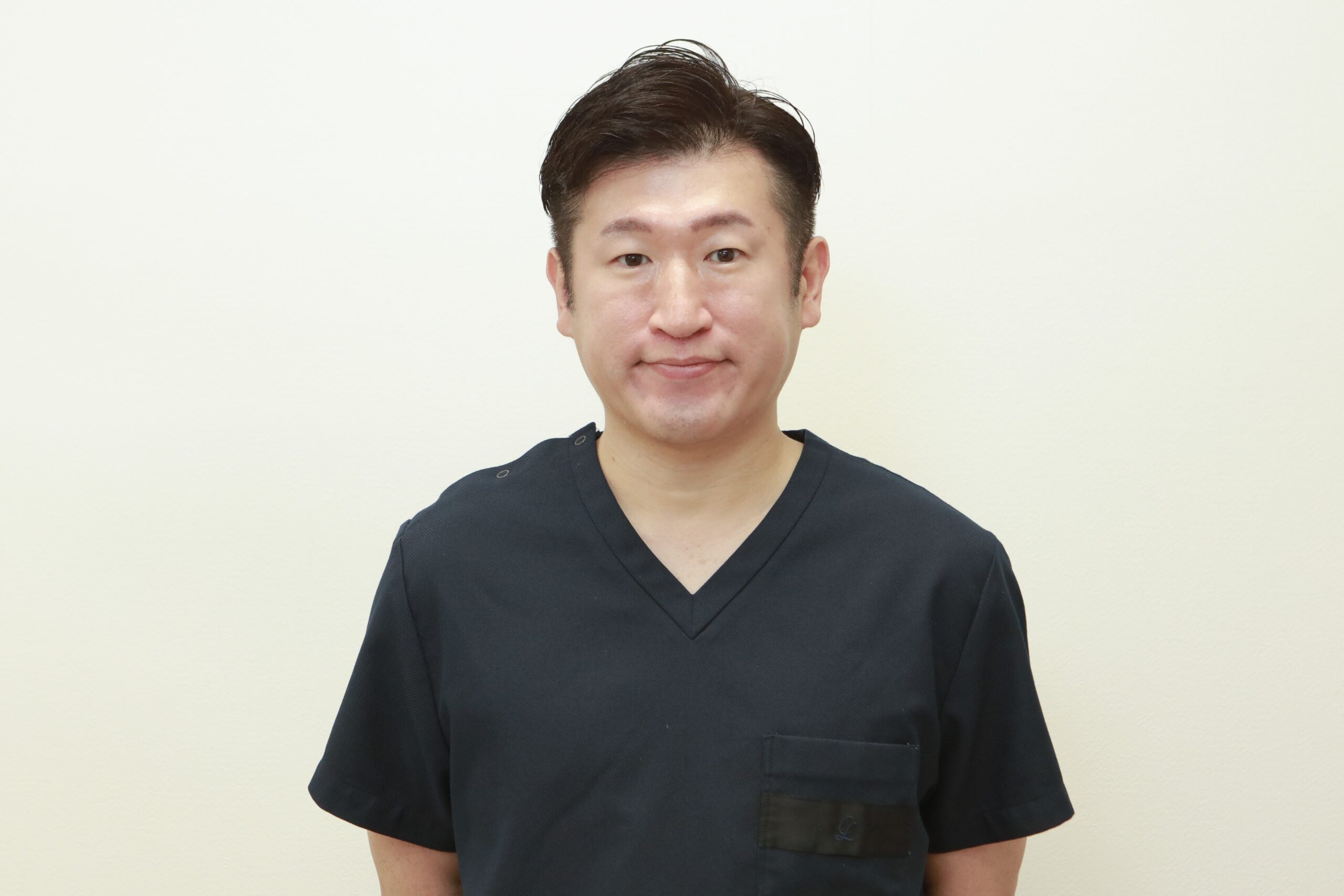
https://tenpakubashi-cl.com/staff/
https://tenpakubashi-cl.jbplt.jp/
目次
新生活のストレスでこんな不調が出ていませんか?よくある症状5選
新生活は、期待に胸を膨らませる一方で、環境の変化によるストレスも抱えやすい時期です。慣れない生活リズムや人間関係、仕事のプレッシャーなど、様々なストレス要因が重なり、心身に不調が現れることがあります。
実は、これらの不調は体が環境の変化に適応しようと頑張っている証拠でもあります。しかし、無理をしすぎると心身のバランスを崩し、慢性的な不調につながる可能性もあるため注意が必要です。つらい症状を我慢せずに、まずはご自身の状態を把握し、適切な対処をすることが大切です。
当院は内科・内視鏡クリニックとして、地域の皆様の健康をサポートしています。内視鏡専門医として消化器系の疾患に精通しているだけでなく、内科全般の診療にも幅広く対応しておりますので、新生活における心身の不調でお悩みの方も、どうぞお気軽にご相談ください。
倦怠感・疲労感
新しい環境では、常に気を張っているため、交感神経という活動時に働く自律神経が優位になりがちです。通常は、休息時には副交感神経が優位に働くことで心身のリラックスが促されますが、ストレス状況下ではこの切り替えがスムーズにいかず、倦怠感や疲労感が慢性化してしまうのです。
例えば、慣れない通勤ラッシュや新しい職場での人間関係に緊張し、帰宅後もなかなかリラックスできない状態が続くと、体は休まる暇がなく、どんどん疲労が蓄積されていきます。
このような状態が続くと、朝起きるのがつらくなったり、日中も集中力が低下したり、仕事や学業のパフォーマンスにも影響が出てしまう可能性があります。
頭痛・肩こり
ストレスを感じると、肩や首の筋肉が緊張し、血行不良を引き起こします。すると、筋肉に十分な酸素や栄養が供給されなくなり、老廃物が蓄積することで、肩こりや頭痛といった症状が現れます。
パソコン作業やスマートフォンの長時間使用など、同じ姿勢を長時間続けることも、筋肉の緊張を悪化させる要因となります。
初期のうちは、肩が重だるい、首が回りにくいといった軽度の症状がみられますが、放置すると慢性的な痛みに発展し、日常生活にも支障をきたすことがあります。ひどい場合は、吐き気を伴うほどの激しい頭痛に悩まされるケースも少なくありません。
食欲不振・胃腸の不調
ストレスは、自律神経のバランスを崩すだけでなく、消化器系の機能にも悪影響を及ぼします。胃酸の分泌過多や胃腸の運動機能の低下により、食欲不振、胃の痛み、吐き気、便秘、下痢といった様々な症状が現れることがあります。
また、新しい生活に伴う食生活の変化も、胃腸の不調を招く一因となります。例えば、外食が増えたり、食事時間が不規則になったりすることで、胃腸に負担がかかり、消化不良を起こしやすくなります。
気分の落ち込み・不安感
新しい環境では、人間関係の構築や仕事のプレッシャーなど、様々なストレス要因に直面します。これらのストレスが過剰になると、脳内の神経伝達物質のバランスが崩れ、気分の落ち込みや不安感といった精神的な症状が現れることがあります。
初期症状としては、ちょっとしたことでイライラしやすくなったり、集中力が低下したりすることが挙げられます。症状が進行すると、趣味や楽しいことに対する興味を失ったり、将来に希望が持てなくなったりするなど、抑うつ状態に陥る可能性もあります。
乳がんの患者さんにおいても、診断や治療に伴うストレスや不安、抑うつ、生活の質(QOL)の低下といった心理的な問題が生じることがあります。適切な心理的サポートは、治療への adherence(服薬遵守や通院など治療への積極的な参加) を高め、治療成績の向上にもつながると考えられています。
睡眠障害(寝つきが悪い、眠りが浅いなど)
ストレスは、睡眠の質にも大きく影響します。寝つきが悪くなったり、夜中に何度も目が覚めたり、朝早くに目が覚めてしまうなど、様々な睡眠障害を引き起こす可能性があります。
質の良い睡眠は、心身の疲労回復に不可欠です。睡眠不足が続くと、日中の倦怠感や集中力の低下を招くだけでなく、免疫力の低下にもつながり、様々な病気にかかりやすくなってしまいます。
天白橋内科内視鏡クリニックでは、こうした新生活におけるストレスによる様々な不調に対応しております。お気軽にご相談ください。
ストレスによる不調のメカニズムと悪化を防ぐ生活習慣4選
新しい環境での生活は、期待とともに不安や緊張も伴います。慣れない人間関係や仕事のプレッシャーなど、ストレスを感じる場面も多いでしょう。ストレスは心だけでなく体にも様々な影響を及ぼし、放置すると慢性的な不調につながる可能性があります。今回は、ストレスが体に及ぼす影響について内科医師の視点から詳しく解説し、悪化を防ぐための生活習慣を4つご紹介します。名古屋市天白区の天白橋内科内視鏡クリニックでは、内視鏡専門医が皆さまの健康をサポートいたします。内科全般のご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
ストレスが体に及ぼす影響
ストレスを感じると、私たちの体はどのように反応するのでしょうか?緊急事態に備え、心拍数を上げたり、筋肉を緊張させたりと、体は戦闘態勢に入ります。これは、自律神経のバランスが崩れ、交感神経が優位になることで起こります。短期的なストレスであれば問題ありませんが、慢性的なストレスに晒されると、この状態が持続し、体に様々な不調が現れます。例えば、胃腸の不調、頭痛、肩こり、動悸、息切れ、めまい、不眠など、多岐にわたります。
ストレスは免疫機能にも影響を及ぼします。ストレスホルモンであるコルチゾールは、過剰に分泌されると免疫細胞の働きを抑制し、感染症にかかりやすくなります。風邪をひきやすくなったり、傷の治りが遅くなったりといった経験はありませんか?それは、ストレスによって免疫力が低下しているサインかもしれません。さらに、長期間にわたるストレスは、生活習慣病のリスクを高めることも知られています。高血圧、糖尿病、脂質異常症などは、ストレスと密接な関係があります。
自律神経の乱れと不調の関係
自律神経は、私たちの意思とは無関係に、呼吸、消化、体温調節など、生命維持に不可欠な機能をコントロールしています。自律神経には、活動時に優位になる交感神経と、リラックス時に優位になる副交感神経の2種類があり、これらがバランスよく働くことで、私たちの体は健康な状態を保つことができます。
ストレスを感じると、交感神経が優位になり、心拍数や血圧が上昇し、血管が収縮します。これは、緊急事態に備えて体がエネルギーを蓄えようとする反応です。しかし、この状態が長く続くと、体に負担がかかり、様々な不調が現れます。例えば、交感神経が優位な状態では、胃腸の働きが抑制されるため、食欲不振や消化不良を起こしやすくなります。また、筋肉が緊張した状態が続くことで、肩こりや頭痛が生じます。一方、副交感神経が優位な状態では、体はリラックスし、修復機能が高まります。質の良い睡眠を得たり、消化機能が促進されたりするのも、副交感神経のおかげです。
ストレスホルモンの影響
ストレスを感じると、副腎皮質からコルチゾールと呼ばれるストレスホルモンが分泌されます。コルチゾールは、血糖値を上昇させ、エネルギーを供給することで、私たちがストレスに対処するのを助けてくれます。しかし、過剰なストレスに長期間さらされると、コルチゾールが過剰に分泌され、様々な悪影響を及ぼす可能性があります。
例えば、過剰なコルチゾールは、免疫機能の低下や、高血圧、糖尿病などのリスクを高める可能性があります。また、コルチゾールは、記憶や学習に関わる脳の領域である海馬の神経細胞にダメージを与えることも知られています。慢性的なストレスは、認知機能の低下やうつ病のリスクを高める可能性があるため、注意が必要です。乳がんの患者さんにおいても、診断や治療に伴うストレスや不安によって、抑うつ、認知機能障害、睡眠障害、QOLの低下といった心理的な問題が生じやすいため、注意が必要です。
規則正しい生活リズムの重要性
ストレスを軽減し、自律神経のバランスを整えるためには、規則正しい生活リズムを心がけることが大切です。人間の体には、約24時間周期で変動する体内時計が備わっています。この体内時計は、睡眠や覚醒、ホルモン分泌、体温調節など、様々な生理機能に影響を与えています。
毎日同じ時間に起床し、3食きちんと食べることで、体内時計が調整され、自律神経の働きが安定します。また、規則正しい生活は、睡眠の質を向上させることにもつながります。睡眠不足はストレスを増大させる要因となるため、十分な睡眠時間を確保することも重要です。
栄養バランスの取れた食事
ストレスに負けない体を作るためには、栄養バランスの取れた食事も欠かせません。ストレスを感じると、体内のビタミンやミネラルが消費されます。特に、ビタミンB群やビタミンCは、ストレスへの抵抗力を高める働きがあるため、積極的に摂取しましょう。
ビタミンB群は、豚肉、鶏肉、魚、卵、大豆製品などに多く含まれています。ビタミンCは、柑橘系の果物、緑黄色野菜、じゃがいもなどに多く含まれています。これらの食品をバランスよく取り入れることで、ストレスに強い体を作ることができます。また、ストレスを感じると甘いものが食べたくなる方もいるかもしれませんが、糖質の過剰摂取は血糖値の乱高下を招き、かえってストレスを増大させる可能性があります。バランスの良い食事を心がけ、健康的な食生活を送りましょう。
天白橋内科内視鏡クリニックで新生活のストレス不調対策!受診の目安と当院の特徴
新生活は、新たな出会いや経験への期待とともに、環境の変化や人間関係、仕事のプレッシャーなど、多くのストレス要因に直面する時期でもあります。ストレスは、心身に様々な影響を及ぼし、放っておくと慢性的な不調につながる可能性があります。当クリニックは、内科・内視鏡クリニックとして、地域の皆さまの健康をサポートしています。内視鏡専門医として消化器系の疾患に精通しているだけでなく、内科全般の診療にも幅広く対応しておりますので、新生活における心身の不調でお悩みの方も、どうぞお気軽にご相談ください。
どんな症状で受診するべき?
新生活に伴うストレスは、倦怠感、頭痛、食欲不振、気分の落ち込み、睡眠障害など、多様な症状を引き起こします。これらの症状は一過性の場合もありますが、2週間以上続く、日常生活に支障が出るほど辛い、強い不安感や抑うつ感がある、自傷行為や自殺願望があるといった場合は、医療機関への受診が必要です。
例えば、新しい仕事でのプレッシャーから夜眠れなくなり、日中の集中力が低下し、ミスが増えてさらにストレスが溜まる、といった悪循環に陥るケースも少なくありません。初期の段階で適切な対応をすることで、慢性化を防ぎ、心身の健康を守ることができます。
また、ストレスは免疫機能を低下させるため、感染症にかかりやすくなることもあります。風邪をひきやすい、傷の治りが遅いなどもストレスのサインかもしれません。
診療内容と費用について
当クリニックでは、風邪やインフルエンザなどの一般的な内科疾患から、生活習慣病、消化器疾患、アレルギー疾患など、幅広い疾患に対応しています。新生活のストレスによる不調についても、丁寧な問診と診察を行い、患者さま一人ひとりに合わせた治療方針を決定します。必要に応じて、血液検査や心電図検査などの検査も行います。
内視鏡専門医による胃カメラ・大腸カメラ検査も可能ですので、消化器系の症状でお悩みの方もご相談ください。費用は、保険診療の場合、3割負担が基本となりますが、検査や処置の内容により異なりますので、詳しくは受付までお問い合わせください。
アクセス方法と駐車場のご案内
当クリニックは、名古屋市営地下鉄鶴舞線「原駅」2番出口より徒歩2分の場所に位置し、公共交通機関でのアクセスが良好です。また、お車でお越しの方のために、提携駐車場もご用意しています。クリニックの周辺には商業施設や飲食店もあり、お買い物のついでにもお立ち寄りいただけます。
ご相談・お問い合わせ方法
ご不明な点やご質問、ご予約などございましたら、お電話または当クリニックのウェブサイトからお問い合わせください。当クリニックは、患者さまのプライバシー保護にも配慮し、安心して受診いただける環境づくりに努めています。
まとめ
新生活はワクワクする反面、慣れない環境でストレスを感じやすい時期でもありますね。 倦怠感や頭痛、食欲不振、気分の落ち込み、睡眠障害…心身に様々な不調が出ていませんか?
これらの症状は、体が環境の変化に適応しようと頑張っているサインかもしれません。 でも、無理は禁物です。 ストレスをためすぎると、慢性的な不調につながることもあるので、早めに対策を取りましょう。
規則正しい生活リズムや栄養バランスの取れた食事を心がけるだけでも、ずいぶんと心身の状態が変わってきますよ。 つらい症状が続く場合は、我慢せずに医療機関に相談することも考えてみてくださいね。
新しい環境でも、健やかに過ごせるよう、ご自身の心と体とゆっくり向き合っていきましょう。
全ては患者さんの「もっと早く治療しとけばよかった・・・」を無くしたいから。
詳しくは当院のホームページ(←こちらをクリック)からどうぞ。



令和7年3月22日
天白橋内科内視鏡クリニック 野田久嗣
・医学博士
・日本内科学会認定内科医
・日本消化器病学会消化器病専門医
・日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医
参考文献
- Penberthy JK, Stewart AL, Centeno CF, Penberthy DR. Psychological Aspects of Breast Cancer. The Psychiatric clinics of North America 46, no. 3 (2023): 551-570.
追加情報
[title]: Psychological Aspects of Breast Cancer.,
乳がんにおける心理的側面
【要約】
乳がんは女性で最も多く診断されるがんであり、ストレス、適応困難、不安、抑うつ、認知機能障害、睡眠障害、身体像の変化、性機能障害、QOL(生活の質)の低下など、様々な心理的症状を伴う。
患者の苦痛スクリーニングとアセスメントにより、治療介入の恩恵を受ける女性を特定することができる。これらの症状に対処することで、治療へのコンプライアンスと、疾患関連転帰、心理的症状、QOLを含む転帰を改善できる。
最も効果的な治療法には、感情表現などの対処スキルを教えること、およびその他の構造化された認知行動療法、対人療法、マインドフルネスアプローチが含まれる。
患者には、がん治療の全過程を通して、これらの心理社会的支援を提供するべきである。
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37500250,
[quote_source]: Penberthy JK, Stewart AL, Centeno CF and Penberthy DR. “Psychological Aspects of Breast Cancer.” The Psychiatric clinics of North America 46, no. 3 (2023): 551-570.