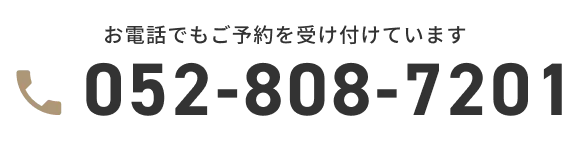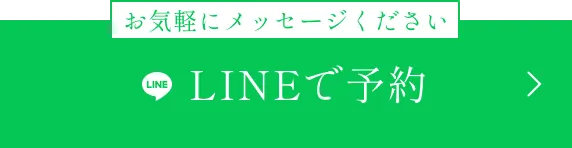「夕方になると靴がきつい」「足が重だるくて疲れやすい」…そんな足のむくみに悩まされていませんか? 実は、足のむくみは、一時的なものから病気のサインまで、様々な原因が潜んでいる身近な症状なのです。長時間同じ姿勢でのデスクワークや立ち仕事、運動不足といった日常的な要因から、静脈瘤やリンパ浮腫、さらには内臓疾患の可能性まで…その原因は多岐に渡ります。 放置すれば健康に悪影響を及ぼすことも。 この記事では、足のむくみの4つのタイプ別原因を徹底解説し、適切な対処法をご紹介します。 もしかしたら、あなたの足のむくみは重要なサインかもしれません。今すぐチェックして、足の健康を守りましょう。
【この記事の著者のご紹介】
みなさんお待たせしました。専門医がお答えシリーズです!
お待たせし過ぎたかもしれませんし、誰もお待ちではないかもしれません。
内視鏡といえば天白橋。内科もやっぱり天白橋。天白橋内科内視鏡クリニックの院長野田です。
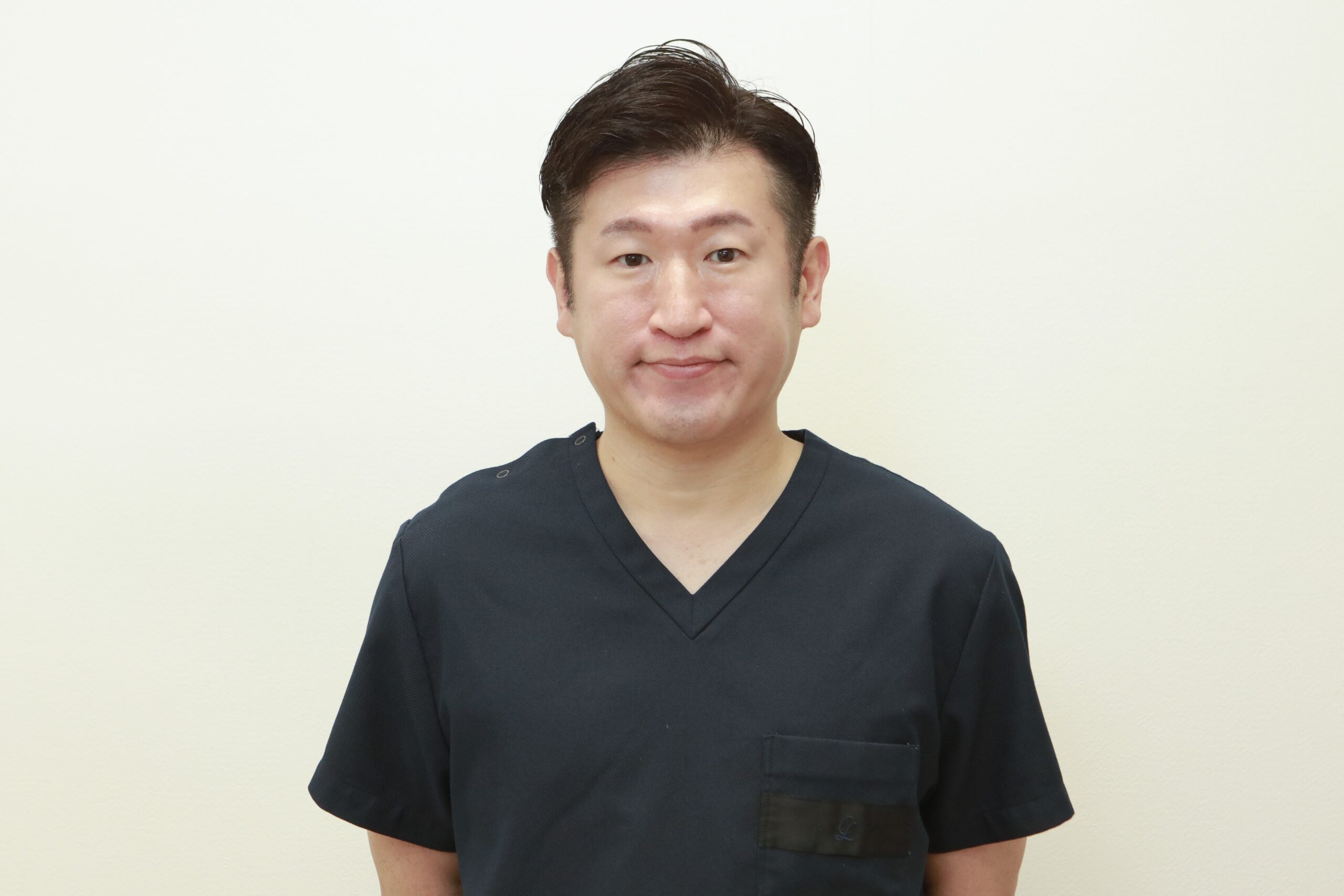
https://tenpakubashi-cl.com/staff/
https://tenpakubashi-cl.jbplt.jp/
足のむくみの原因をチェック!4つのタイプ別解説
「夕方になると足がむくんで靴がきつい」「足が重だるくて疲れやすい」といった足のむくみは、多くの方が経験する症状です。一時的なものから、病気のサインである場合まで、その原因は様々です。放置すると健康に悪影響を及ぼす可能性もあるため、原因を正しく理解し、適切な対処をすることが重要です。
当クリニックは内科・内視鏡クリニックであり、内視鏡専門医ではありますが、内科全般のご相談に応じています。発熱外来から内視鏡、美容医療まで、幅広く対応していますので、足のむくみについてもどうぞお気軽にご相談ください。今回は、足のむくみの原因を4つのタイプに分けて詳しく解説します。
血行不良によるむくみ
心臓から送り出された血液は、動脈を通って全身に運ばれ、静脈を通って心臓に戻ります。この循環が滞ると、静脈に血液が溜まり、血管から水分が漏れ出てむくみが生じます。
長時間同じ姿勢でのデスクワークや立ち仕事、運動不足は、足の筋肉のポンプ機能を低下させ、血行不良を招きます。デスクワーク中に足を組む癖がある方は要注意です。また、加齢による血管の弾力性の低下や、肥満による心臓への負担増加も、血行不良によるむくみのリスクを高めます。
例えば、飛行機のエコノミークラス症候群も、長時間同じ姿勢でいることで血行不良が起こり、足の静脈に血栓ができる病気です。血栓が肺に飛ぶと、呼吸困難などを引き起こす可能性があります。このように、血行不良によるむくみは、時に命に関わる病気を引き起こす可能性があるため、軽視せず、日頃から予防を心がけることが大切です。
リンパ浮腫によるむくみ
リンパ管は、体内の老廃物や余分な水分を回収・運搬する下水道のような役割を果たしています。このリンパ管が詰まったり損傷したりすると、リンパ液がうまく流れなくなり、むくみが生じます。これがリンパ浮腫です。
リンパ浮腫は、がんの手術後や放射線治療後の後遺症として発症することがあります。乳がんの手術でリンパ節を郭清した場合などに起こりやすいです。また、細菌感染や寄生虫感染、生まれつきのリンパ管の異常などによっても発症することがあります。
リンパ浮腫の特徴として、むくみが片足だけに現れることが多いこと、皮膚が硬くなることなどが挙げられます。血行不良によるむくみとは異なり、リンパ浮腫の場合、足を高くしてもむくみが改善しにくいという特徴があります。
静脈瘤によるむくみ
静脈には、血液が逆流しないように弁がついています。この弁が壊れて血液が逆流すると、静脈が瘤(こぶ)のように膨らんでしまいます。これが静脈瘤です。静脈瘤ができると、血液の循環が悪くなり、むくみが生じやすくなります。
静脈瘤は、立ち仕事が多い方や妊娠中の方、遺伝的要因を持つ方に多く見られます。また、静脈瘤は、足のだるさや痛み、こむら返りを伴うこともあります。進行すると皮膚が変色したり、潰瘍ができたりすることもあります。
その他の病気(腎臓病、心臓病、肝臓病など)によるむくみ
足のむくみは、腎臓病、心臓病、肝臓病などの内臓疾患のサインである場合があります。これらの病気は、体内の水分バランスを崩し、むくみを引き起こします。
例えば、腎臓の機能が低下すると体内の水分や老廃物がうまく排出されず、むくみが現れます。心臓の機能が低下すると血液を全身に送るポンプ機能が弱まり、静脈に血液が溜まりやすくなり、むくみを生じます。肝臓病になると、血液中のアルブミンというタンパク質が減少し、血管内の水分が血管外に漏れ出しやすくなり、むくみが起こります。
これらの病気によるむくみは、全身に現れることが多いですが、特に足に出やすい傾向があります。息切れや動悸、倦怠感などの症状を伴うこともあります。足のむくみだけでなく、他の症状も出ている場合は、早めに医療機関を受診してください。
稀ではありますが、静脈筋腫症を原因とするバッド・キアリ症候群のように、下肢の浮腫を伴う重篤な疾患も存在します。バッド・キアリ症候群は、肝臓から心臓に戻るための主要な静脈が詰まる病気で、腹痛、腹部膨満感、両下肢の浮腫などの症状が現れます。子宮筋腫や子宮摘出術の既往がある場合は、注意が必要です。
当院では、上記のような様々な原因による足のむくみに対して、適切な検査と治療を行っていますので、お気軽にご相談ください。
足のむくみの診断方法と天白橋内科での診察
足のむくみは、誰しも経験する身近な症状です。しかし、その裏には深刻な病気が隠れている可能性もあるため、軽く見てはいけません。天白橋内科内視鏡クリニックでは、内科全般のご相談に応じており、足のむくみについても専門的な知見に基づいて診療を行っています。どうぞお気軽にご相談ください。
診察の流れ
当院では、患者さん一人ひとりの症状や不安に寄り添い、丁寧な診察を心がけています。足のむくみの診察は、以下の流れで行います。
-
問診: まずは、むくみの症状について詳しくお伺いします。いつからむくみ始めたのか、一日の中でむくみが強い時間帯はあるか、痛痒さや熱感などの症状を伴うか、他に何か気になる症状はあるか、過去の病気や現在服用している薬などについてもお聞きします。これらの情報は、むくみの原因を特定するための重要な手がかりとなります。
-
視診・触診: 次に、実際に足を拝見し、むくみの程度や部位、皮膚の状態などを確認します。皮膚の色つやや温度、血管の拡張なども重要な情報です。また、皮膚を指で数秒間押して、へこみがすぐに戻るかどうかも確認します。へこみが戻らない場合は、むくみが強い可能性があります。
-
検査: 問診や視診・触診の結果に基づき、必要に応じて検査を行います。超音波検査、血液検査、尿検査などが挙げられます。これらの検査によって、むくみの原因をより詳しく調べることができます。
-
診断: 検査結果を総合的に判断し、むくみの原因を診断します。
-
治療: 診断結果に基づき、患者さんに最適な治療法をご提案します。場合によっては、他の医療機関と連携して治療を進めることもあります。
触診、視診による診断
触診では、むくんでいる部分の皮膚を指で押してみて、弾力や硬さ、痛み、熱感の有無などを確認します。視診では、むくみの程度や部位、皮膚の色つやや血管の状態などを観察します。例えば、皮膚が赤く熱を持っていたり、血管が蛇行して膨らんでいたりする場合は、炎症や静脈瘤の可能性があります。
超音波検査、血液検査などの精密検査
超音波検査では、血管の状態をリアルタイムで確認できます。血管の狭窄や閉塞、血栓の有無、血流の状態などを評価することで、静脈瘤や深部静脈血栓症などの診断に役立ちます。血液検査では、腎臓や肝臓の機能、コレステロール値、炎症反応などを調べます。腎臓や肝臓の機能が低下していると、むくみが起こりやすくなります。また、血液検査で炎症反応が強い場合は、感染症などが原因でむくみが起こっている可能性があります。尿検査では、腎臓の機能を評価します。腎臓の機能が低下すると、尿にタンパク質が漏れ出てむくみが起こることがあります。
他の医療機関との連携
当院では、患者さんに最適な医療を提供するために、他の医療機関と積極的に連携しています。必要に応じて、専門性の高い医療機関をご紹介いたします。例えば、下肢静脈瘤の手術が必要な場合は、血管外科のある病院をご紹介いたします。また、むくみの原因が心臓や腎臓などの病気である場合、稀ではありますが、静脈筋腫症を原因とするバッド・キアリ症候群のように重篤な疾患も存在します。子宮筋腫や子宮摘出術の既往がある場合は特に注意が必要です。このような場合は、それぞれの専門医と連携して治療を進めていきます。患者さんに安心して治療を受けていただけるよう、最善を尽くしますので、ご安心ください。
足のむくみを改善!日常生活のケアと治療法
足のむくみ。夕方になると靴がきつくなったり、足がだる重くなったり…。多くの方が経験するこの症状、実は放置すると健康に悪影響を及ぼす可能性もあるんです。今回は、ご自宅でできるケアから医療機関での治療まで、足のむくみを改善する方法をわかりやすくご紹介します。足のむくみは、血液循環やリンパの流れの滞りによって起こります。心臓から足に送られた血液は、ふくらはぎの筋肉のポンプ作用によって心臓に戻っていきます。しかし、長時間同じ姿勢でいたり、運動不足だったりすると、このポンプ機能がうまく働かず、血液が足に溜まってしまうのです。すると、血管から水分が漏れ出し、むくみとして現れるのです。まるで、蛇口を閉め忘れて水が溢れ出ているような状態ですね。
当クリニックは内科・内視鏡クリニックです。内視鏡専門医ではありますが、内科全般のご相談に応じています。発熱外来から内視鏡、美容医療まで幅広く対応していますので、足のむくみについてもどうぞお気軽にご相談ください。
家庭でできるケア方法(着圧ソックス、マッサージ、ストレッチなど)
まずは、今日からすぐに始められるケア方法をご紹介します。
-
着圧ソックス/ストッキング: 足首からふくらはぎにかけて段階的に圧力をかけることで、血液を心臓に戻すポンプ機能をサポートします。まるで、足に優しく包帯を巻いているようなイメージです。特に、立ち仕事やデスクワークが多い方におすすめです。
-
マッサージ: 足先から心臓に向かって優しくマッサージすることで、リンパの流れを促し、老廃物の排出を助けます。リンパ管は、体内の老廃物を運ぶ下水道のような役割を果たしています。マッサージによって、この下水道の流れをスムーズにする効果が期待できます。
-
ストレッチ: ふくらはぎの筋肉を伸ばすストレッチは、血行促進に効果的です。ふくらはぎは、第二の心臓とも呼ばれ、血液循環において重要な役割を担っています。ストレッチによってふくらはぎの筋肉を柔らかくすることで、ポンプ機能を活性化させることができます。
-
足を高くして休む: 足を心臓より高くすることで、重力に逆らって血液を心臓に戻しやすくします。寝る前に、クッションや毛布などを足の下に敷いて、10~15分ほど足を高くして休みましょう。
食事療法(塩分制限、カリウム摂取など)
むくみは体内の水分バランスが崩れることで起こるため、食事内容の見直しも重要です。
-
塩分制限: 塩分の摂りすぎは、体内に水分を溜め込み、むくみを悪化させます。塩分を摂りすぎると、体は水分を薄めようと水を溜め込むため、むくみが生じやすくなります。濃い味噌汁を飲んだ後、顔がむくんでしまうのと同じ原理です。
-
カリウム摂取: カリウムは、体内の余分な塩分を排出する働きがあります。カリウムを多く含む食品、例えば、バナナやほうれん草などを積極的に摂り入れましょう。塩分を摂りすぎてしまったら、カリウムでバランスを取るイメージです。
運動療法
適度な運動は、血行やリンパの流れを促進し、むくみの改善に効果的です。ウォーキングや軽いジョギングなど、無理のない範囲で継続して行うことが大切です。運動不足だと、足の筋肉のポンプ機能が低下し、むくみが起こりやすくなります。
薬物療法(利尿剤など)
むくみがひどい場合や、他の病気によって引き起こされている場合は、医師の指示のもと、薬物療法が行われることがあります。利尿剤は、尿の量を増やすことで、体内の余分な水分を排出し、むくみを軽減します。ただし、利尿剤は脱水症状や電解質異常などの副作用を起こす可能性があるので、自己判断で服用することは避け、必ず医師に相談しましょう。子宮筋腫や子宮摘出術の既往がある女性では、稀ではありますが、静脈筋腫症を原因とするバッド・キアリ症候群のように、下肢の浮腫を伴う重篤な疾患も存在します。バッド・キアリ症候群は、肝臓から心臓に戻るための主要な静脈が詰まる病気で、腹痛、腹部膨満感、両下肢の浮腫などの症状が現れます。
医療機関での治療(弾性ストッキング、硬化療法、手術など)
家庭でのケアや薬物療法で改善しない場合は、医療機関での治療が必要になる場合があります。当院では、足のむくみの原因を特定し、症状に合わせた適切な治療法をご提案します。
-
弾性ストッキング: 医療用の弾性ストッキングは、着圧ソックスよりも圧迫力が強く、むくみの改善により効果的です。
-
硬化療法: 静脈瘤が原因のむくみの場合、硬化療法が行われることがあります。静脈瘤に薬剤を注入し、静脈を閉塞させることで、血液の流れを正常に戻します。
-
手術: 静脈瘤やリンパ浮腫が重症の場合、手術が必要となることがあります。
足のむくみは、放置すると様々な病気を引き起こす可能性があります。日頃から適切なケアを行い、足の健康を守りましょう。少しでも気になることがあれば、お気軽にご相談ください。
まとめ
足のむくみ、気になりますよね。放っておくと深刻な病気が隠れていることもあるので、軽視できません。
むくみの原因は、長時間同じ姿勢での作業や運動不足による血行不良、リンパの流れの滞り、静脈瘤など様々です。
家庭では、着圧ソックスやマッサージ、ストレッチ、足を高くして休むなどでケアできます。また、塩分を控え、カリウムを多く含む食品を摂ることも効果的です。適度な運動も大切です。
これらのケアで改善しない場合は、医療機関への相談も検討しましょう。内科では、症状に合わせた検査や治療(弾性ストッキング、硬化療法、手術など)が受けられます。
むくみを放置すると様々な病気を引き起こす可能性も。日頃からケアを心がけ、足の健康を守りましょう。少しでも気になることがあれば、気軽に医療機関に相談してみてくださいね。
全ては患者さんの「もっと早く治療しとけばよかった・・・」を無くしたいから。
詳しくは当院のホームページ(←こちらをクリック)からどうぞ。



令和7年4月11日
天白橋内科内視鏡クリニック 野田久嗣
・医学博士
・日本内科学会認定内科医
・日本消化器病学会消化器病専門医
・日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医
参考文献
- Gan J, Ma X, Shao J, Wang J, Cao D. Intravenous leiomyomatosis presenting as Budd-Chiari syndrome: a case report and literature review. Orphanet journal of rare diseases 20, no. 1 (2025): 49.
追加情報
[title]: Intravenous leiomyomatosis presenting as Budd-Chiari syndrome: a case report and literature review.,
静脈筋腫症を原因とするバッド・キアリ症候群:症例報告と文献レビュー
【要約】
静脈筋腫症(IVL)が原因のバッド・キアリ症候群(BCS)は稀な疾患であり、その診断と治療法の確立にはさらなる報告と綿密な評価が必要である。
本論文では、IVLに続発するBCSの症状を示した49歳女性の症例を報告し、過去に報告されたIVLによるBCSの症例3例をレビューした。
4例における発症平均年齢は54.8歳であり、1例を除く全てが子宮筋腫、筋腫摘出術、または子宮摘出術の既往歴を持っていた。腹痛、腹部膨満感または腹囲増加、両下肢浮腫が共通した症状であった。IVLとBCSの臨床診断は、超音波検査、CT、MRIなどの画像検査と臨床症状に基づいて主に決定される。肝静脈流出路閉塞を軽減するための外科的介入が最も重要な治療法である。
下大静脈と右心房の病変がBCSの特徴を示す患者で、子宮筋腫または子宮摘出術の既往歴がある場合、IVLによるBCSを考慮すべきである。完全な腫瘍切除が唯一の根治的治療法であり、できるだけ早期に実施する必要がある。
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39905462,
[quote_source]: Gan J, Ma X, Shao J, Wang J and Cao D. “Intravenous leiomyomatosis presenting as Budd-Chiari syndrome: a case report and literature review.” Orphanet journal of rare diseases 20, no. 1 (2025): 49.