女性の身体が大きく変化する更年期。この時期は、卵巣機能の低下により様々な不調が現れます。 ほてりや発汗、イライラ、気分の落ち込みなど、更年期障害の症状は多岐にわたり、日常生活に大きな影響を与えることも。 実は、更年期世代の女性の10~15%は鉄欠乏性貧血を抱えているという報告もあります。 この記事では、更年期障害の症状や原因、治療法、そして更年期障害と間違えやすい疾患まで、詳しく解説します。 更年期を快適に過ごすためのヒントが満載ですので、ぜひご一読ください。
【この記事の著者のご紹介】
みなさんお待たせしました。専門医がお答えシリーズです!
お待たせし過ぎたかもしれませんし、誰もお待ちではないかもしれません。
内視鏡といえば天白橋。内科もやっぱり天白橋。天白橋内科内視鏡クリニックの院長野田です。
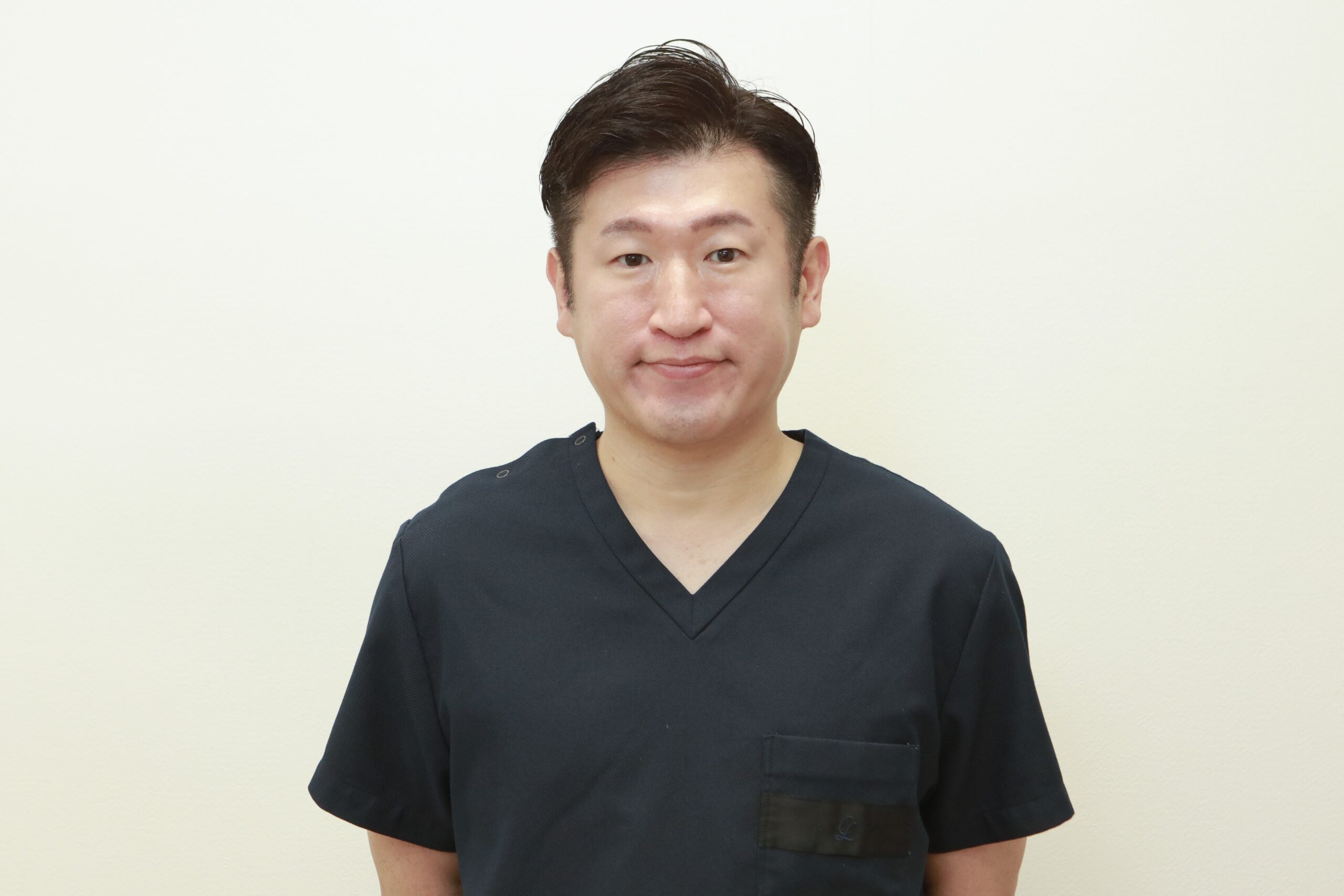
https://tenpakubashi-cl.com/staff/
https://tenpakubashi-cl.jbplt.jp/
更年期障害の症状と原因4つのポイント
更年期は、女性の身体が大きく変化する時期です。卵巣機能の低下によって女性ホルモンの分泌が変化し、それに伴い様々な症状が現れることがあります。更年期障害は、この時期特有の症状に悩まされる状態を指します。更年期障害の症状と原因を理解し、適切なケアを行うことは、この時期をより快適に過ごすためにとても重要です。内科全般を診療する当院では、更年期障害のご相談も承っておりますので、どうぞお気軽にお話しください。
更年期障害の代表的な症状5選(ほてり、発汗、イライラなど)
更年期障害の代表的な症状として、下記の5つが挙げられます。
-
ほてり(ホットフラッシュ): 突然、まるで火照ったように顔や首、胸、背中などが熱くなる症状です。同時に、汗が噴き出すこともあります。温度変化の激しい環境や、辛いものを食べた時などに起こりやすく、数秒から数分続く場合もあります。
-
発汗: 特に夜間や睡眠中に大量の汗をかくことがあります。寝汗でパジャマやシーツがびしょ濡れになることもあります。
-
イライラ: 感情の起伏が激しくなり、些細なことでイライラしやすくなります。例えば、家族にきつく当たってしまったり、些細なミスに過剰に反応してしまったりするなど、日常生活に影響が出ることがあります。
-
うつ状態: 気分が落ち込み、何事にも意欲がわかない状態が続きます。以前は楽しめていた趣味や活動にも興味を失い、喜びを感じにくくなります。
-
不眠: 寝つきが悪くなったり、夜中に何度も目が覚めてしまう、朝早く目が覚めてしまうなど、睡眠の質が低下します。日中の倦怠感や集中力の低下につながることもあります。
これらの症状以外にも、頭痛、めまい、動悸、肩こり、腰痛、疲労感、関節痛、性交痛、膣の乾燥、頻尿、尿漏れなど、実に様々な症状が現れることがあります。更年期障害は、更年期に現れる様々な症状の総称であり、その症状は多岐にわたります。
症状の現れ方:初期、中期、後期の変化
更年期障害の症状は、閉経に至る過程で変化することがあります。閉経とは、卵巣機能の低下により月経が永久に停止した状態を指し、最後の月経から12ヶ月以上月経がない場合に閉経と診断されます。閉経の平均年齢は50歳前後ですが、個人差が大きいため40代前半で閉経を迎える方もいれば、50代後半まで月経が続く方もいらっしゃいます。
-
閉経移行期(初期): 月経周期が25日以内になったり、39日以上になったりと、月経周期が乱れ始め、月経の期間や出血量が変化することがあります。同時に、ほてりや発汗などの症状が現れ始める方もいます。
-
閉経前後(中期): ほてりや発汗などの症状がピークを迎える時期です。精神的な症状(イライラ、不安感、抑うつなど)も強く現れることがあります。
-
閉経後(後期): ほてりや発汗などの症状は徐々に軽快していきます。しかし、皮膚や粘膜の乾燥、尿トラブル、骨粗鬆症などのリスクが高まります。
更年期障害の症状は個人差が大きく、症状の出方や期間も様々です。症状が軽く、日常生活に支障がない方もいれば、症状が重く、仕事や家事が困難になる方もいます。更年期世代の女性の10~15%は鉄欠乏性貧血を抱えているという報告もあります。
女性ホルモン低下と自律神経の乱れの関係
更年期障害の多くの症状は、女性ホルモン(エストロゲン)の減少と自律神経の乱れが関係しています。エストロゲンは、自律神経のバランスを保つ役割も担っているため、エストロゲンが減少すると、体温調節や発汗、血管収縮などの機能をコントロールする自律神経が乱れやすくなります。自律神経の乱れは、ほてりや発汗、動悸、不眠、消化器系の不調など、様々な症状を引き起こします。
加齢やストレス、生活習慣の乱れ、睡眠不足、栄養バランスの偏りなども自律神経の乱れを助長する要因となります。更年期を迎えると、女性ホルモンの減少だけでなく、環境の変化や生活習慣の乱れなどが重なり、自律神経が乱れやすくなるため、注意が必要です。
放置するとどうなる?リスクと対処法
更年期障害の症状を放置すると、日常生活に支障をきたすだけでなく、うつ病、骨粗鬆症、脂質異常症、高血圧、動脈硬化などのリスクが高まる可能性があります。更年期障害は、適切な治療と生活習慣の改善によって症状を軽減することができます。更年期障害かなと思ったら、我慢せずに医療機関を受診しましょう。
当院では、血液検査によって貧血や甲状腺機能の異常など、更年期障害と似た症状を引き起こす他の病気がないかを確認します。更年期障害の治療として、ホルモン補充療法、漢方薬の処方、生活習慣の改善指導など、患者様一人ひとりに合わせた治療プランをご提案しています。更年期障害かもしれない、と思ったら、お気軽にご相談ください。
更年期障害と間違えやすい疾患3選
更年期障害かな?と感じたら、婦人科を受診する方が多いと思いますが、更年期障害と似た症状が現れる疾患は他にもあります。ご自身の症状を正しく理解し、適切な診療科を受診することは、早期の診断と治療に繋がります。今回は、更年期障害と間違えやすい3つの疾患について、内科医の視点から詳しく解説します。
貧血:種類と原因、更年期との関連性
貧血は、血液中の赤血球の数が減少したり、赤血球に含まれるヘモグロビンという酸素を運ぶタンパク質が減少した状態です。酸素が全身に行き渡りにくくなるため、疲れやすさ、動悸、息切れ、めまい、顔色が悪くなるといった症状が現れます。
貧血には様々な種類がありますが、大きく鉄欠乏性貧血、巨赤芽球性貧血、溶血性貧血の3つに分類されます。この分類は、貧血の原因に基づいています。
最も多いのは鉄欠乏性貧血です。鉄はヘモグロビンの材料となるため、鉄分が不足するとヘモグロビンが作られなくなり、貧血になります。女性は月経による出血があるため、男性に比べて鉄欠乏性貧血になりやすい傾向があります。特に更年期では、月経不順や過多月経によって貧血が悪化することがあります。医学文献によれば、妊娠可能な年齢の女性の10~15%が鉄欠乏性貧血を抱えているという報告もあります。
巨赤芽球性貧血は、ビタミンB12や葉酸の不足が原因で起こります。これらのビタミンは、赤血球の正常な発達に必要不可欠です。不足すると、未熟な大型の赤血球が作られ、貧血になります。
溶血性貧血は、赤血球が通常よりも早く壊れることで起こります。遺伝的な要因や自己免疫疾患などが原因となることがあります。
更年期になると、女性ホルモンのバランスが乱れ、自律神経が不安定になります。その結果、貧血と似たような症状(だるさ、めまいなど)が現れることがあります。更年期に貧血を合併している場合も多く、当院では血液検査で貧血の有無や種類を調べることが可能です。
PMS(月経前症候群):症状の特徴と対処法
PMS(月経前症候群)は、月経が始まる約2週間前から心身に様々な不調が現れる症状です。症状は月経開始とともに軽くなり、消失します。PMSの症状は人それぞれで、200種類以上もの症状が報告されており、その中には、イライラ、怒りっぽくなる、気分の落ち込み、不安、集中力の低下、乳房の張りや痛み、頭痛、腹痛、むくみなどがあります。
PMSの原因は完全には解明されていませんが、女性ホルモンの変動や神経伝達物質のバランスの乱れが関与していると考えられています。月経周期によって症状が現れたり消えたりするのが特徴です。
更年期障害とPMSは、どちらも女性ホルモンの変動が関係しているため、症状が似ている部分があります。しかし、PMSは月経のある女性に起こるもので、更年期障害は閉経に伴う症状です。PMSの症状が辛い場合は、我慢せずに婦人科に相談しましょう。症状に合わせて、鎮痛剤、低用量ピル、漢方薬などを処方してもらえます。日常生活では、カフェインやアルコールを控え、バランスの良い食事、適度な運動、十分な睡眠を心がけることが大切です。
甲状腺疾患:更年期との鑑別ポイント
甲状腺ホルモンは新陳代謝を調整する重要なホルモンです。甲状腺ホルモンが過剰に分泌されるバセドウ病と、分泌が不足する橋本病は、更年期障害と似た症状を引き起こすことがあります。
バセドウ病では、動悸、息切れ、発汗、イライラ、不安感、体重減少など、更年期障害と共通する症状が現れます。橋本病では、倦怠感、むくみ、便秘、体重増加、記憶力の低下、うつ症状などが見られます。これらの症状も更年期障害と似ています。
更年期障害との鑑別には、血液検査で甲状腺ホルモンの値を測定することが重要です。当院では、内科全般を診療しており、甲状腺ホルモンの血液検査も可能ですので、更年期障害かもしれない、あるいは甲状腺に不安があるという方は、お気軽にご相談ください。更年期障害と甲状腺疾患を併発している場合もありますので、自己判断せずに医療機関を受診することをお勧めします。
天白橋内科内視鏡クリニックでの更年期障害治療3つの特徴
更年期は、誰しもが経験するライフステージの変化です。この時期は、卵巣機能の低下に伴い、女性ホルモンの分泌が急激に減少することで、心身に様々な不調が現れることがあります。
天白橋内科内視鏡クリニックでは、内科全般の診療に加え、更年期障害の治療にも力を入れています。これは、更年期障害の症状が他の内科疾患と非常に似ていることが多いため、的確な診断と適切な治療の提供が必要だと考えているからです。例えば、動悸や息切れは更年期障害だけでなく、心臓病や甲状腺疾患の可能性も考えられます。当院では、内視鏡専門医として培ってきた身体全体を診る確かな知識と経験を活かし、患者様一人ひとりの症状に寄り添い、最適な治療法をご提案いたします。
1. 血液検査と問診による的確な診断
当院では、更年期障害の診断において、血液検査と丁寧な問診を重視しています。
しかし、更年期障害の診断は血液検査の結果のみで判断するものではありません。なぜなら、更年期障害の症状は非常に多様であり、個人差も大きいからです。そのため、患者様一人ひとりの症状や生活習慣、既往歴などを詳しく伺う丁寧な問診が不可欠です。
例えば、ほてりや発汗は更年期障害の代表的な症状ですが、同じような症状が甲状腺機能亢進症でも現れることがあります。問診を通して患者様の症状を詳しく把握することで、更年期障害だけでなく、他の疾患の可能性も考慮した上で、より正確な診断につなげることができます。
2. プラセンタなど患者様に最適な治療プラン
更年期障害の治療法は、患者様の症状や生活への影響、そしてご希望に合わせてご用意しています。代表的な治療法としては、当院ではプラセンタ、漢方薬でしょうか。
漢方薬療法は、体質改善を目的とした治療法です。更年期障害の症状は多岐にわたるため、患者様の症状に合わせて複数の漢方薬を組み合わせることもあります。「なんとなく体調が悪い」「何となくだるい」といった漠然とした不調にも対応できるのが漢方薬のメリットです。
当院では、それぞれの治療法の長所・短所を丁寧にご説明した上で、患者様に最適な治療プランをご提案いたします。更年期障害の治療は、画一的な方法ではなく、患者様一人ひとりに合わせたオーダーメイドの治療が重要です。
3. 日常生活の改善指導:食事、運動、睡眠
更年期障害の症状を和らげ、より快適に過ごすためには、日常生活の改善も重要です。栄養バランスの良い食事、適度な運動、質の高い睡眠は、更年期だけでなく、健康な生活を送る上で欠かせない要素です。
食事に関しては、エストロゲン様作用を持つ大豆イソフラボンを多く含む大豆製品や、骨粗鬆症予防に効果的なカルシウムを多く含む牛乳や小魚、貧血予防に効果的な鉄分を多く含む赤身の肉やレバーなどを積極的に摂り入れることをおすすめします。
運動は、ウォーキングやヨガなど、無理なく続けられる軽い運動を習慣的に行うことが大切です。適度な運動は、血行を促進し、自律神経のバランスを整える効果が期待できます。また、ストレス発散にも効果的です。
睡眠は、心身の疲れを癒すために必要不可欠です。毎日同じ時間に寝起きする、寝る前にカフェインを摂らない、リラックスできる環境を作るなど、睡眠の質を高める工夫をしましょう。
当院では、患者様一人ひとりのライフスタイルに合わせた具体的なアドバイスも行っております。更年期は、人生における大きな転換期です。天白橋内科内視鏡クリニックは、患者様とともに更年期を乗り越え、健康で充実した毎日を送れるよう、全力でサポートいたします。
まとめ
更年期障害は、女性ホルモンの減少によって起こる様々な症状の総称です。ほてりや発汗、イライラ、気分の落ち込みなど、多様な症状が現れ、日常生活に大きな影響を与えることもあります。
更年期障害かな?と思ったら、まずは医療機関を受診しましょう。天白橋内科内視鏡クリニックでは、血液検査や丁寧な問診を通して的確な診断を行い、ホルモン補充療法、漢方薬療法など、患者様一人ひとりに最適な治療プランをご提案いたします。
また、日常生活における食事、運動、睡眠の改善についても、具体的なアドバイスを行っています。更年期は、人生100年時代において、まだ折り返し地点。更年期を健やかに乗り越え、その先の豊かな人生を楽しむために、私たちと一緒に考えていきましょう。
全ては患者さんの「もっと早く治療しとけばよかった・・・」を無くしたいから。
詳しくは当院のホームページ(←こちらをクリック)からどうぞ。



令和7年4月11日
天白橋内科内視鏡クリニック 野田久嗣
・医学博士
・日本内科学会認定内科医
・日本消化器病学会消化器病専門医
・日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医
参考文献
- Gattermann N, Muckenthaler MU, Kulozik AE, Metzgeroth G, Hastka J. The Evaluation of Iron Deficiency and Iron Overload. Deutsches Arzteblatt international 118, no. 49 (2021): 847-856.
追加情報
[title]: The Evaluation of Iron Deficiency and Iron Overload.,
【要約】
西洋諸国では、妊娠可能な年齢の女性の10~15%が鉄欠乏性貧血に罹患している。一方、輸血による慢性治療や遺伝性ヘモクロマトーシスによる鉄過剰ははるかに稀である。
本レビューは、鉄欠乏と鉄過剰の病態生理、臨床症状、診断評価に関する選択的検索によって得られた関連出版物を基にしている。
鉄欠乏の主な原因は、栄養不良と出血である。鑑別診断には、ヘプシジンレベルが病的に上昇する稀な先天性疾患である鉄不応性鉄欠乏性貧血(IRIDA)や、より一般的な慢性疾患性貧血(慢性炎症性貧血)が含まれる。慢性炎症性貧血では、インターロイキン-6の影響下でヘプシジンが増加し、腸管からの鉄吸収が阻害される。鉄過剰は、長期的な輸血療法または鉄代謝の先天性異常(ヘモクロマトーシス)によって生じる。その診断評価は、臨床的および検査所見、画像検査、および特定の変異解析に基づいている。
鉄代謝の分子病態生理に関する理解が深まるにつれて、鉄欠乏と鉄過剰の評価が向上し、将来的には鉄補充療法やキレート療法だけでなく、ヘプシジン調節系の標的薬理学的調節も可能になる可能性がある。
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34755596,
[quote_source]: Gattermann N, Muckenthaler MU, Kulozik AE, Metzgeroth G and Hastka J. “The Evaluation of Iron Deficiency and Iron Overload.” Deutsches Arzteblatt international 118, no. 49 (2021): 847-856.


